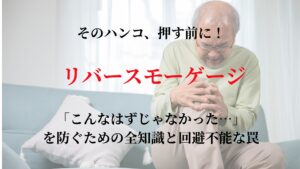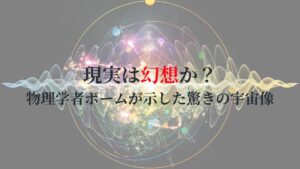税務署から「申告内容に誤りがあるので修正申告書を提出してください」という連絡を受けた場合、多くの納税者は不安を感じ、言われるままに応じてしまうことがあります。しかし、このような要請は法的にどのような性質を持つのでしょうか。本稿では、行政手続法の観点から修正申告の要請を「行政指導」として位置づけ、納税者が持つ権利と適切な対応策について解説します。
修正申告の法的性質:行政手続法から読み解く納税者の権利
1. 修正申告の法的性質:行政指導とは何か
税務調査の結果として「申告内容に誤りがあるので修正申告書を提出してください」という要請を受けることは、納税者にとって珍しくない経験です。しかし、この税務調査後の修正申告の要請は、法的にどのような性質を持つのでしょうか。結論から言えば、このような修正申告の要請も「行政指導」に該当します。
1.1 行政指導としての修正申告要請
行政指導とは、行政手続法第2条第6号において次のように定義されています。
「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」
税務調査を経て税務署が行う修正申告の要請は、調査によって把握した事実に基づき、納税者に対して適正な納税義務の履行を求めるものです。しかし、重要なのは、たとえ税務調査の結果として行われる場合でも、修正申告の要請自体には法的拘束力がなく、「自主的な協力」という前提の上に成り立っているという点です。
税務調査によって事実関係が明らかになったとしても、最終的に修正申告を行うか否かの判断は納税者自身に委ねられています。税務署は調査結果に基づいて修正申告を促すことはできますが、納税者がそれに従わない場合には、税務署長の権限で更正処分を行うことになります。
1.2 修正申告と更正処分の法的性質の違い
修正申告と更正処分には、以下のような重要な法的性質の違いがあります:
- 行為の主体:修正申告は納税者自身が「自ら提出するもの」であるのに対し、更正処分は「税務署からの処分」です。
- 法的性格:修正申告は納税者が誤りを認めて自発的に行う行為ですが、更正処分は行政機関による処分行為です。
- 不服申立ての可否:修正申告は自ら納得して提出するものであるため、その内容自体に対する不服申立てはできません。一方、更正処分の場合は税務署からの処分であるため、処分内容に納得できない場合に不服申立てをすることができます。
この点について、最高裁判所も平成18年10月24日の判決において、「修正申告は、納税者が自らの意思と責任に基づいて行うものであり、税務署長による更正とは異なる」という趣旨の判断を示しています。
1.3 修正申告に応じた場合の法的意味
税務調査において修正申告に応じることには、重要な法的意味があります。修正申告は「処分」ではなく納税者自身の行為であるため、一度修正申告を行うと、その内容に対して不服申立てができなくなります。一方、税務署長による更正処分であれば、それは「賦課決定処分」となり、不服申立ての対象となります。
つまり、修正申告に応じることで、納税者は自らの意思で申告内容を修正したことになり、その内容に対して争う権利を放棄したことになるのです。ただし、修正申告をしても加算税については別途で不服申立てが可能ですし、修正申告に対して更正の請求を行うこともできます。
1.4 更正処分と立証責任
更正処分が行われた場合、立証責任は基本的に税務署側にあります。税務署は更正処分を行う際に、その処分が正当であることを立証する必要があります。
税務署は、納税者が修正申告に応じない場合、更正処分を行うためには、その処分に耐えうる資料・証拠を集める必要があります。これは、更正処分が「処分」として不服申立ての対象となるためです。
不服申立てが行われた場合、税務署は自らの処分が適法かつ妥当であることを証明しなければなりません。つまり、更正処分の根拠となる事実や法令の適用が正しいことを示す責任があります。
1.5 実務上の考慮点
実務的な観点からは、修正申告に応じることで税務署との交渉やバーターが可能になるというメリットがあります。例えば「Cは認容しますのでAとBで修正申告に応じて」といった交渉が可能になり、結果として納税者に有利になる場合もあります。一方、更正処分の場合はこのような交渉の余地はなく、税務署は不服申立てに耐えうる資料・証拠を集める必要があるため、調査期間が長引く可能性もあります。
支払うべき追徴税額は、修正申告でも更正処分でも同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、修正申告でも更正処分でも、同じ100万円を支払うことになり、加算税や延滞税の金額も同じになります。
しかし、否認内容に納得がいかないのに流れに任せて修正申告を行うと、後から反論するチャンスはなくなります。このため、税務調査終盤で調査官も税理士も修正申告でという流れになったとしても、本当に指摘事項に納得できるか考えることが重要です。
更正処分を受けたからといって、以後税務署から不利益な取り扱いを受けるわけではありません。あくまでも、見解の相違があり、それが最後まで埋まらなかったというだけの意味です。
このように、修正申告に応じるか否かは単なる手続きの問題ではなく、納税者の権利や実務上の利害に関わる重要な判断なのです。
2. 行政指導と税務調査の明確な違い
税務署から連絡があった場合、それが「行政指導」なのか「税務調査」なのかを正確に理解することは、納税者の権利保護の観点から非常に重要です。両者には明確な法的区分があり、それによって納税者の対応や結果が大きく異なります。
2.1 法的位置づけの違い
税務調査は、国税通則法に明記された質問検査権に基づいて行われる公権力の行使です。具体的には、納税者の課税標準等または税額等を認定する目的、その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で税務職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)を指します1。
一方、行政指導は「調査に該当しない行為」であり、特定の納税義務者の課税標準等または税額等を認定する目的で行う行為に至らないもの(とどまるもの)とされています1。行政指導は納税者の自発的な見直しを要請するものであり、税務調査よりもマイルドな手続として位置づけられています3。
2.2 手続きの違い
税務調査と行政指導では、開始方法にも明確な違いがあります:
- 税務調査の場合:口頭または文書により、税務調査官が「これは税務調査です」と納税者に対し明確に調査宣言することから始まります。この調査宣言を経て初めて、税務調査官は質問検査権を行使して帳簿等を調べることが可能となります3。
- 行政指導の場合:「お尋ね文書」などの形で、申告内容の確認や書類の提出要請が行われます。質問検査権の行使はなく、納税者の自発的な協力を求める形で進められます3。
平成25年の国税通則法改正により、税務調査手続が法定化され、行政指導と税務調査の区分がより明確になりました3。事務運営指針には「納税義務者等に対し調査または行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行うこと」と規定されています1。
2.3 加算税の取り扱いの違い
行政指導と税務調査の最も重要な実務上の違いは、加算税の取り扱いです:
- 行政指導の場合:行政指導に基づいて修正申告書を提出しても、原則として過少申告加算税は賦課されません35。
- 税務調査の場合:税務調査官から誤りを指摘され修正申告書を提出すると、原則として10%の過少申告加算税が賦課されます3。
これは、行政指導による修正申告は「更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたもの」には当たらないとされているためです1。
2.4 行政指導の具体例
行政指導には以下のような具体例があります:
- 提出された納税申告書に法令により添付すべき書類が添付されていない場合の自発的な提出要請1
- 申告書の計算誤り、転記誤り、記載漏れ等がある場合の自発的な見直し要請1
- 税法の適用誤りがあると思われる場合の基礎的情報提供要請1
- 納税申告書の提出義務の有無を確認するための基礎的情報提供要請1
- 源泉徴収税額の過不足徴収額がある場合の自主納付等の要請1
2.5 実務上の注意点
行政指導だからといって軽視することは危険です。お尋ね文書に回答せず無視したり、適当な虚偽の内容で回答したりすると、行政指導から税務調査に移行されることがしばしばあります3。特に無申告の場合、最初は行政指導としてのお尋ね文書が送付されてくるものの、回答しない状況が続くと、税務調査に移行するケースが多いです3。
税務署側は納税者に対する接触率を一定以上に保ちたいと考えており、申告内容の調査必要度によって税務調査と行政指導を使い分けています。調査必要度が高い(申告内容に相当疑義のある)ものは税務調査として、調査必要度が低い(若干気になる点がある程度の)ものは行政指導として対応する傾向があります3。
近年の感染症問題やリモートワークの影響もあり、今後はお尋ね文書等による簡易な接触である行政指導の件数が増加し、実地の税務調査の件数は減少する傾向にあると予測されています3。
3. 納税者の権利と法的保護
納税者の権利保護は、憲法の基本原理に基づく重要な法的課題です。日本では諸外国と比較して納税者権利保護の法制化が遅れていますが、納税者には様々な権利が保障されています。
3.1 憲法に基づく納税者の権利
納税者の権利は、日本国憲法の基本原理である基本的人権の尊重、国民主権、平和主義から当然に導き出される権利です3。憲法11条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と規定しており、これが納税者権利保護の大前提となります1。
税務署及び税務の執行にあたる公務員は憲法遵守義務を負っており(憲法99条)、国民の基本的人権を保障しなければなりません1。また、憲法98条は憲法を「国の最高法規」と定め、憲法に反する行為は「全部又は一部、その効力を有しない」と規定しています1。
3.2 申告納税制度と納税者の権利
国税通則法16条は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則」と定めています14。この申告納税制度は、主権者である国民が自分の税金を計算し、申告し、納税することを通じて政治に参加する憲法上の民主的権利です6。
税務署長の処分により確定することは例外的であり、基本は納税者の申告で確定します。そのため、税務署員が調査に来たときに、納税者が「調査理由」を聞くのは当然の権利とされています4。
3.3 税務調査における納税者の権利
税務調査において納税者には以下のような権利が保障されるべきとされています:
- 事前通知を受ける権利:強制調査を除く全ての税務調査に事前通知を受ける権利があります2。全商連は税務署に「調査の際は事前に連絡し、その理由を述べること」を求めた請願署名運動に取り組み、1974年に第72回国会の衆議院大蔵委員会で「事前通知の励行と調査理由の開示」を内容とする請願を採択させています4。
- 丁重な扱いを受ける権利:納税者は、課税庁が行う税務調査、徴収等において公正かつ丁重に扱われる権利を有します3。納税者の行った申告は、具体的な反証がない限り、すべて誠実かつ適正なものとして尊重されるべきです3。
- 専門家の援助を受ける権利:納税者は自らの選択により、税務調査など課税庁との対応において専門家の援助を受ける権利とともに第三者の立会を求める権利を有します3。
- プライバシーを保護される権利:納税者は自分のプライバシーを侵害されない権利を有します3。
3.4 納税者権利憲章の必要性
納税者権利憲章は、納税者が保障されるべき権利を具体的に知らせるために制定されるものです3。納税者の権利憲章は、1975年フランスの「税務調査に関する憲章」制定に始まり、各国に広がりました6。
日本では、1989年の消費税の導入と反対運動の高まりの中、納税者権利憲章の制定を求め、多くの団体が憲章案を示しました6。2009年の民主党政権誕生で同党が公約した「納税者権利憲章の制定」に期待が広がりましたが、最終的には2011年度税制改定で権利憲章ではなく、国税通則法の改定にとどまりました6。
現在、経済協力開発機構(OECD)に加盟する主要国の中で納税者権利憲章が制定されていないのは日本だけとなっています6。納税者権利憲章は国際的な最低限の基準であり、憲章を制定した国では、納税者は公正・丁寧に扱われ、権利を尊重された税務行政が当たり前に行われています6。
3.5 不服申立制度による権利救済
納税者の正当な権利・利益を救済するための制度として、「異議申立て」「審査請求」「訴訟」があります8。これらは税務調査により更正処分などを受けた場合に、税務署と納税者との見解が対立した際に利用できる制度です8。
不服申立時において納税者は、制度の説明を十分に受ける権利、迅速かつ慎重な審理を受ける権利、審理に第三者性及び透明性を担保される権利などを有します2。
このように、納税者の権利と法的保護は憲法や法律によって保障されていますが、実務上はまだ多くの課題があり、納税者権利憲章の制定など、さらなる法的整備が求められています。
4. 修正申告を促された場合の適切な対応策
税務調査の結果として修正申告を促された場合、納税者はどのように対応すべきでしょうか。この章では、納税者の権利を守りながら適切に対応するための具体的な方策について解説します。
4.1 指摘内容の精査と検討
税務署から修正申告を促された場合、まず指摘内容を十分に精査することが重要です。税務署の指摘が正しいかどうかを判断するためには、以下の点に注意しましょう。
- 指摘事項の法的根拠を確認する:税務署の指摘が税法上の根拠に基づいているかを確認します。曖昧な説明や根拠が不明確な場合は、具体的な法令や通達の提示を求めることも検討しましょう。
- 事実関係の確認:指摘された内容が事実と一致しているかを確認します。帳簿や証憑書類を再度確認し、事実誤認がないかをチェックしましょう。
- 専門家への相談:税理士などの専門家に相談し、指摘内容の妥当性について意見を求めることも有効です。特に複雑な税務問題の場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
4.2 修正申告に応じるか否かの判断
指摘内容を精査した結果、どのように対応するかを判断する必要があります。
- 指摘内容に納得できる場合:指摘が正当であると判断した場合は、修正申告に応じることを検討します。この場合、できるだけ早く修正申告書を提出し、不足税額を納付することで、延滞税の額を抑えることができます。
- 指摘内容に納得できない場合:指摘に疑問や異議がある場合は、修正申告に応じず、更正処分を受ける選択肢もあります。修正申告の勧奨に応じなかったからといって、基本的には不利な取扱いを受けることはありません。
- 部分的に納得できる場合:一部の指摘には同意するが、他の部分には同意できない場合は、同意できる部分についてのみ修正申告を行うという選択肢もあります。
4.3 修正申告と更正処分の選択
修正申告と更正処分のどちらを選択するかは、以下の点を考慮して判断しましょう。
- 不服申立ての可能性:修正申告を行った場合、その内容自体に対する不服申立てはできなくなります。一方、更正処分であれば、不服申立てが可能です。将来的に争う可能性がある場合は、更正処分を選択する方が有利かもしれません。
- 加算税と延滞税:修正申告と更正処分では、支払うべき追徴税額は同じですが、タイミングによっては延滞税の額に差が出ることがあります。
- 税務署との関係:修正申告に応じることで税務署との交渉の余地が生まれる場合もあります。例えば、一部の指摘事項については認めることで、他の部分については譲歩を引き出せる可能性もあります。
4.4 修正申告後の対応
修正申告を行った後も、以下の点に注意が必要です。
- 更正の請求の可能性:修正申告後に誤りに気づいた場合、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求を行うことができます。以前は1年以内とされていましたが、平成23年度の国税通則法改正により5年に延長されました。
- 附帯税の取り扱い:修正申告に伴い課される過少申告加算税などの附帯税については、独自に不服申立ての対象となります。修正申告自体は争えなくても、附帯税については争える可能性があります。
4.5 実務上のポイント
- 税務代理人の活用:税理士などの税務代理人がいる場合、調査結果の説明等を代理人に対して行ってもらうことも可能です。納税者の同意があれば、税務代理人のみに説明等を行うこともあります。
- 証拠資料の保管:修正申告や更正の請求を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要です。関連する証拠資料は適切に保管しておきましょう。
- 時間的余裕を持った対応:修正申告の判断は慎重に行う必要がありますが、あまり長く放置すると延滞税が増加する可能性があります。適切なタイミングで判断することが重要です。
このように、修正申告を促された場合の対応は、単に税務署の指示に従うだけでなく、納税者自身の権利と利益を守るための重要な判断となります。状況に応じて適切な選択をし、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが賢明です。
5. 行政指導に従わなかった場合の法的リスク
行政指導に従う法的義務はないものの、実務上はいくつかのリスクが存在します。納税者が税務署からの修正申告の要請に従わなかった場合、どのような法的リスクがあるのか検討しましょう。
5.1 行政処分への移行リスク
行政指導は行政処分の前段階として位置づけられることが多く、行政指導に従わない場合、税務署は更正処分という行政処分に移行する可能性があります39。修正申告の要請に応じなかった場合、税務署長の権限で更正処分が行われることになります。
更正処分は税務署からの一方的な処分であるため、納税者の意見が反映されにくくなるというデメリットがあります。また、更正処分を行うために税務署は不服申立てに耐えうる証拠を集める必要があるため、より詳細な調査が行われる可能性もあります。
5.2 立入検査などの調査強化
行政指導に従わない場合、事実上「行政から目を付けられた状態」となり、立入検査などのより厳格な調査を受けるリスクが高まります7。税務署は、修正申告に応じない納税者に対して、より詳細な調査を行い、課税要件事実を明らかにしようとする場合があります。
5.3 公表などによる社会的信用への影響
一部の行政指導では、従わなかった場合に公表されるケースがあります7。税務分野では一般的ではありませんが、特に法人の場合、税務コンプライアンスの問題として社会的信用に影響する可能性があります。
5.4 加算税と延滞税の負担
修正申告に応じず更正処分となった場合でも、加算税や延滞税の金額自体は修正申告の場合と同じです。しかし、更正処分までの時間がかかることで、結果的に延滞税の額が増加する可能性があります。
5.5 法的リスクへの適切な対応
行政指導に従わない場合のリスクに対しては、以下のような対応が考えられます:
- 根拠法規の確認:行政指導の根拠となる法規を確認し、従わなかった場合の法的帰結を理解しておくことが重要です7。
- 専門家への相談:行政指導の内容や法的根拠について、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、適切な対応を検討できます3。
- 不合理な行政指導への対応:行政指導の内容や理由が不合理な場合は、行政機関に対して従う意思がないことを明示し、行政指導の中止を求めることも検討できます5。
- 立証責任の認識:更正処分となった場合、立証責任は基本的に税務署側にあることを認識しておくことが重要です。税務署は更正処分が適法かつ妥当であることを証明する必要があります。
5.6 行政手続法による保護
行政手続法第32条第2項では、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と規定されています13。つまり、修正申告の要請に従わなかったという理由だけで、納税者が不利益な取扱いを受けることは法律上禁止されています。
しかし、実務上は行政指導に従わないことが行政処分のきっかけとなることがあるため、単に「行政指導だから従わなくても大丈夫」と安易に判断することは避けるべきです3。
このように、行政指導に従わない場合には様々な法的リスクが存在しますが、それらを適切に理解し対応することで、納税者の権利を守りながら適切な判断を行うことが可能となります。
6章 まとめ:納税者が知っておくべき権利と責任
本稿では、修正申告の法的性質と納税者の権利について詳しく検討してきました。最後に、納税者が知っておくべき権利と責任について総括します。
6.1 納税者の基本的権利
憲法に基づき、納税者には以下のような基本的権利が保障されています:
- 自発的な申告・納税の権利:申告納税制度は納税者の権利であり、自ら申告し納税することは主権者としての重要な権利の行使です14。修正申告する権利も納税者側にあります4。
- 公正・丁重に扱われる権利:すべての納税者は、誠実な納税者として尊重され、公正かつ丁重に扱われる権利を有します1。
- 適正手続きを受ける権利:課税処分に当たっては、事前にその理由を十分知らされ、聴聞や反論の機会が保障されるべきです1。
- 不服申立ての権利:税務署の処分に不服がある場合、再調査の請求や審査請求、訴訟を通じて救済を求める権利があります2。
6.2 納税者の責任
権利と同時に、納税者には以下のような責任も存在します:
- 納税の義務:憲法30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と規定しています3。これは国民の三大義務の一つとされています。
- 正確な申告と記録保持:納税者は正確な申告を行い、必要な記録を適切に保持する責任があります。
- 税金の使途への関心:納税者は税金の使いみちに十分関心を持つことも大切です3。
6.3 行政指導と修正申告に関する重要ポイント
- 修正申告の法的性質:修正申告の要請は行政指導であり、法的拘束力はありません。納税者には従うか従わないかの選択権があります。
- 修正申告と更正処分の違い:修正申告は納税者自身の行為であり、一度行うと内容に対する不服申立てはできません。一方、更正処分は税務署からの処分であり、不服申立ての対象となります。
- 立証責任:更正処分の場合、立証責任は基本的に税務署側にあります。税務署は処分が適法かつ妥当であることを証明する必要があります。更生処分は、税務署側にとっても負担が増えるため、効率性を要求される税務署の職員は、更生処分に移行することを必ずしも歓迎しません。
6.4 納税者権利憲章の必要性
現在、OECD加盟国の中で納税者権利憲章が制定されていないのは日本だけとなっています1。納税者権利憲章は、納税者と国家の間の相互の信頼や敬意、責任の関係を発展させ、納税者のコンプライアンスを促進する役割を持ちます5。
平成23年度税制改正法案では、国税通則法に新たな第4条を挿入し、国税庁長官が「納税者権利憲章」を作成して公表するとされていましたが4、最終的には国税通則法の改正にとどまりました。国税通則法第1条の目的規定を改正し、「税務行政において納税者の権利、利益の保護を図る」とされ、税務調査を行う場合の各種手続きに関して明確化するとしました78。
6.5 最後に
納税者は、自らの権利を理解し、適切に行使することで、公正な税務行政を実現する一助となります。同時に、納税の義務を果たすことで社会の一員としての責任を全うすることができます。税務署からの修正申告の要請に対しては、その法的性質を理解した上で、自らの判断で対応することが重要です。
修正申告を促された場合、単に税務署の指示に従うのではなく、指摘内容を精査し、必要に応じて専門家に相談した上で、自らの権利と責任を踏まえた適切な判断をすることが望ましいでしょう。
(終わり)