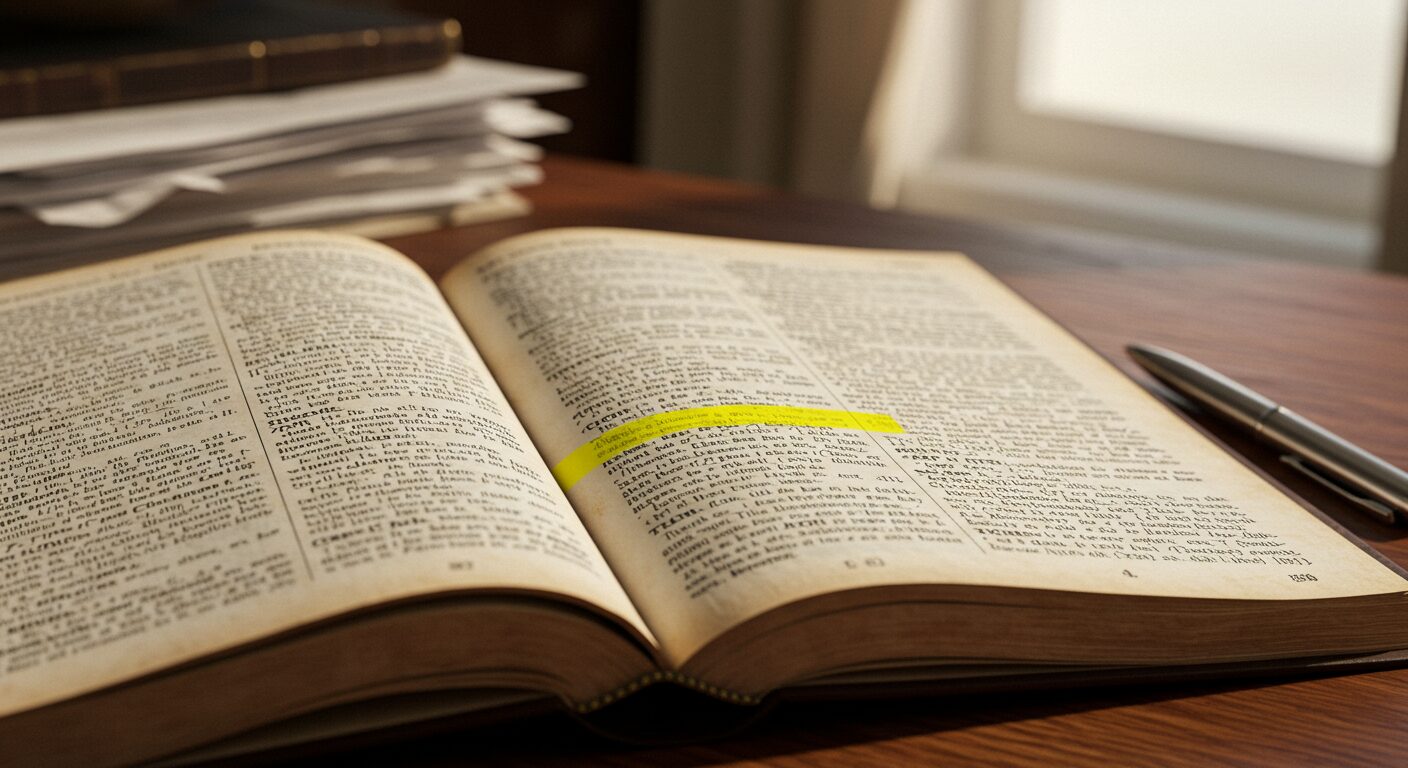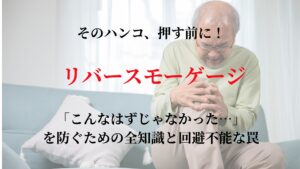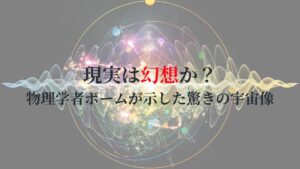生活保護の申請窓口で申請書類を受理してもらえないケースが報告されています。本記事では、行政書士の視点から行政手続法と生活保護法の条文に基づき、申請権の法的保障と窓口対応の問題点について客観的に解説します。
生活保護申請と行政手続法:申請書類不受理の法的問題
1章 はじめに:生活保護申請拒否の実態
1.1 窓口対応の現状
生活保護の窓口では、申請を希望する人が申請書を受け取れないという事態が全国各地で発生しています。この問題は「水際作戦」とも呼ばれており、「地方公共団体が生活保護のための財政負担を軽減する目的で、生活保護申請をさせないように指導、助言を行うこと」を指します1。
具体的な事例として、横浜市神奈川区の福祉事務所では、所持金が9万円で住まいを失った女性が生活保護の申請を希望したにもかかわらず、職員が申請を退け、記録に「申請の意思なし」と記載するという事案が発生しました2。
また、札幌市白石区では姉妹が孤立死した事案で、姉が福祉事務所を3回訪れていたにもかかわらず「相談」の段階にとどまり「申請」まで至らなかったケースや、北九州市門司区では男性が孤立死した事案で、福祉事務所を2回訪れていたものの申請書が交付されなかったという事例も報告されています1。
多くの福祉事務所では、申請の前に「相談」という段階を設けており、この段階で申請に至らないよう様々な対応がなされています。「受付行って、『すいませーん、生活保護の申請書くださーい』と言ったら、『はいはーい。ちょっと待ってねー』と出てくるだろうか?出てこない。代わりに出てくるのは、『ちょっとその前にお話しをうかがわせてもらっていいですかねー』と言ってくる相談員だ」という実態が報告されています1。
1.2 法的観点からの問題提起
このような窓口対応は法的観点から重大な問題をはらんでいます。生活保護法第7条では申請権が、同法第24条では実施機関の義務が明確に規定されています。また、行政手続法の観点からも、申請を受け付けないという対応は違法行為にあたります。
足立区の例では、「足立福祉事務所福祉課の総合相談窓口で相談を受けた者に対し保護申請書を渡さないといういわゆる『水際対応』(申請抑制行為)にあたる対応があった」ことが公式に検証されています6。
こうした違法な申請拒否が生じる背景には、被保護者数の増加と福祉事務所の業務負担の増大があります。生活保護の被保護者数は平成23年7月に現行制度下で過去最高となり、その後も増加傾向にあります3。また、福祉事務所では社会福祉法で定められている「市部:被保護世帯80世帯ごとに1人」という現業員の配置基準と実態が乖離しており、平成24年度の全国平均では被保護世帯93世帯ごとに1人となっています3。
しかし、業務負担の増大や財政的な問題があるとしても、法律で保障された申請権を侵害することは許されません。本稿では、このような生活保護申請拒否の実態を行政手続法と生活保護法の観点から分析し、申請者の権利を守るための法的根拠を明らかにしていきます。
2. 行政手続法における申請権の保障
2.1 行政手続法第7条の規定
行政手続法第7条は、申請に対する行政機関の基本的な義務を定めた重要な条文です。同条は「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない」と規定しています4。
この条文の重要なポイントは、行政機関の審査義務が発生する時点を「申請がその事務所に到達したとき」と明確に定めていることです。つまり、行政機関が申請書を「受理」するという行為を経なくても、申請書が行政機関の事務所に物理的に到達した時点で、行政機関には審査義務が発生するのです7。
これは、従来の行政実務において見られた「申請を『受理』しなければ審査義務が発生せず、『受理』するか否かは行政庁の裁量に委ねられる」という前提の下で、申請を長期間放置したり、「受理」前の行政指導により申請内容を変更させたりする運用を是正するための規定です7。
裁判例においても、大阪地裁平成15年5月8日判決では「行政庁は、申請書が行政庁の事務所に到達したときには、そのときから当該申請書による申請について審査し、応答する義務を負う」と判示されています9。また、申請者の同意なく申請書を返戻する行為は行政手続法第7条に違反すると明確に示されています9。
2.2 申請に対する行政機関の法的義務
行政手続法は、申請に対する行政機関の法的義務として、以下のような規定を設けています。
- 審査開始義務: 前述の通り、申請が事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければなりません(第7条)4。
- 理由提示義務: 申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、同時にその理由も示さなければなりません(第8条)4。
- 審査基準の設定・公開義務: 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するために必要とされる具体的基準(審査基準)を設定し(第5条)、原則として公にしておかなければなりません(第5条第3項)4。これは法的義務であり、努力義務ではありません3。
- 標準処理期間の設定・公開: 申請から処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め(努力義務)、定めた場合には公にしておかなければなりません(第6条、法定義務)34。
- 情報提供義務: 行政庁は、申請者からの求めに応じて、できる限り、申請に必要な書類やその具体的な手続について、情報提供するよう努めることになっています(第9条第2項)1。
- 進捗状況の情報提供: 申請者から問い合わせがあった場合、結論の出る時期の見通しについて、情報を提供するよう努めることになっています(第9条第1項)1。
これらの規定により、行政手続法は申請者の権利を保障し、行政機関の恣意的な判断や対応を防止する仕組みを構築しています。特に第7条の規定は、申請書を受け取らない、受け取っても放置しておくなどの取扱いを明確に禁止しており1、生活保護申請における「水際作戦」のような申請権侵害を法的に防止する根拠となっています。
なお、申請者は、行政機関の不作為(申請をしたのに相当の期間内に何らの処分をすべきにもかかわらず、これをしないこと)に対して、行政不服審査法に基づく「不作為についての審査請求」をすることも可能です1。これは申請権を実効的に保障するための重要な救済手段となっています。
3. 生活保護法における申請の権利
3.1 生活保護法第7条の申請権
生活保護法第7条は「申請保護の原則」を定めており、生活保護は原則として申請に基づいて行われることを規定しています7。具体的には、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」と定められています1。
この規定には重要な意味があります。まず、生活保護を受ける権利は憲法第25条の生存権に基づく権利であり、その権利を実現するための手続きとして申請権が法律上保障されています。申請権者は要保護者本人に限定されず、「扶養義務者」や「その他の同居の親族」も申請権を有していることが明記されています1。
また、申請保護の原則は、行政側の恣意的な判断で保護を開始・不開始とすることを防ぐ機能を持っています。ただし、生活保護法第7条には但し書きがあり、「要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる」とされています。これは「職権保護」と呼ばれ、生命の危機など緊急の場合に備えた例外規定です7。
3.2 同法第24条の実施機関の義務
生活保護法第24条は、保護の申請手続きと実施機関の義務について規定しています。同条第1項では、保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を保護の実施機関に提出しなければならないとされています。ただし、申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではないとのただし書きが付されています4。
申請書には、
①要保護者の氏名及び住所又は居所
②申請者が要保護者と異なるときは申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
③保護を受けようとする理由
④要保護者の資産及び収入の状況
⑤その他必要な事項
を記載することとされています4。
重要なのは、生活保護法第24条第5項(平成25年12月の法改正前は第3項)の規定です。これによれば、「保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない」とされています25。
この規定は、申請があった場合に実施機関に調査・決定・通知の義務を課すものであり、申請を拒否する権限は実施機関に与えられていません。また、決定までの期限についても、原則として申請があった日から14日以内、特別な理由がある場合でも30日以内と法定されています2。
日本弁護士連合会は、現行法の「開始の申請があったときは」という表現を行政手続法第7条と整合させ、「申請が到達したときは」と明確にすべきだと提言しています3。これは、申請書が「受理」されなければ実施機関に調査の義務がないかのような誤った認識を防ぐためです。
生活保護の申請は口頭でも可能であり、特別の事情がある場合には申請書の提出が不要とされています6。これは、申請者の状況に配慮した規定であり、申請権を実質的に保障するものです。
横浜市の検証報告書によれば、「生活保護の実施機関は、相談者の申請意思を確認し、相談者から申請意思が示された場合は、必ず申請を受け付けなければなりません。申請を希望する方にはもちろんのこと、ためらっている方には申請を促すなど、相談者の申請権を尊重しなければなりません」と明記されています9。
4章 申請不受理の違法性
4.1 行政手続法違反の具体的事例
申請書の不受理は行政手続法第7条に違反する行為として、複数の裁判例で違法性が指摘されています。行政手続法第7条は「申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない」と規定しており、これは「到達主義」と呼ばれる原則を確立しています1。
具体的な違法事例として、申請書を一方的に送り返す行為が挙げられます。地方公共団体が申請者の意向に応じないことを理由に一方的に申請書を送り返す行為は、申請後の審査・応答を拒否していることになり、違法とされています1。
生活保護の文脈では、福岡地裁小倉支部平成23年3月29日判決(小倉北自殺事件)が重要です。この事件では、申請権侵害の要件が明確にされました。被保護者が保護利用を継続できることを認識した上で任意かつ真摯に辞退を申し出たといえること、および被保護者に経済的自立の目途があり保護廃止によって急迫した事態に陥るおそれがないことが、保護廃止の要件として必要であるとされました2。
また、行政機関が申請書を返却する行為は事実行為であり、それ自体は行政処分ではないとする裁判例もあります。しかし、行政手続法7条は「受理」の概念を排斥しており、申請の「受理」は事務処理手続上の行為にすぎず、処分とはいえないものとされています3。これは、申請書の返却という事実行為によって申請権を侵害することはできないという考え方に基づいています。
総務省の行政手続法Q&Aでも、「申請書が役所に届いたら、その役所は遅滞なく審査を開始することになっており、申請を受け取らない、受け取っても放置しておくなどの取扱いは許されない」と明確に述べられています5。
4.2 最高裁判例からみた申請権侵害
申請権侵害に関する最高裁判例としては、行政手続法の施行前の事例ですが、旅券法事件判決(最高裁昭和60年1月22日判決)が重要です1。この判決では、申請拒否処分の理由提示について判断されました。
また、生活保護に関連する最高裁判例として、永住外国人申請却下事件(最高裁平成26年7月18日判決)があります。この事件では、永住者の在留資格を有する外国人の生活保護申請却下処分が争われました。最高裁は、生活保護法による保護の適用を求める申請に対する却下決定について判断しましたが、行政措置として行われる事実上の保護の申請が却下された場合にこれを訴訟等で争うことが認められる余地は残されているとしています2。
申請権侵害に関する法的理解として重要なのは、申請書の受領拒否は行政手続法7条によって「法的に無意味なもの」とされていることです。申請の到達によって直ちに審査義務が生じると規定されているため、「不受理」行為(受理拒否行為)は法的に無効となります7。
したがって、申請書の受領拒否は、明らかに申請拒否処分の体裁を整えているものを除いては、申請取下げ指導や内容変更指導といった行政指導の一環として行われる事実上の行為にすぎないと理解すべきであり、それ自体を行政処分とみて抗告訴訟により攻撃することはできません7。しかし、このような行為の違法性は国家賠償訴訟において争われることになります。
生活保護の文脈では、本来申請後に行われるべき給付要件の審査を実質的に申請前に行うために申請書を受け取らないことは申請権の侵害にあたるとされています8。これは、生活保護法が定める申請保護の原則を無視し、行政手続法が保障する申請権を侵害する行為として違法性が認められるものです。
5章 適法な申請手続きの流れ
5.1 法律に基づく正しい申請プロセス
生活保護の申請手続きは、生活保護法と行政手続法に基づいて適法に行われなければなりません。正しい申請プロセスは以下のとおりです。
- 申請の意思表示: 申請者が福祉事務所の窓口で生活保護の申請意思を表明します。この時点で、福祉事務所は申請書を交付する義務があります。
- 申請書の提出: 申請者は生活保護法第24条第1項に基づき、申請書を保護の実施機関に提出します。申請書には、要保護者の氏名・住所、申請理由、資産・収入状況などを記載します。ただし、申請書を作成できない特別な事情がある場合は、口頭による申請も認められています。
- 申請の到達: 行政手続法第7条により、申請書が福祉事務所に到達した時点で、実施機関には審査開始義務が発生します。「受理」という行為は法的には不要であり、申請書の物理的な到達をもって申請が成立します。
- 調査の実施: 福祉事務所は申請を受けて、要保護者の生活状況、資産状況、収入状況、扶養義務者の状況などについて調査を行います。この調査は申請を受けた後に行われるべきものであり、調査前に申請を拒否することはできません。
- 保護の要否判定: 調査結果に基づき、保護の要否、種類、程度及び方法を決定します。
- 決定の通知: 生活保護法第24条第5項に基づき、決定内容を申請者に書面で通知します。決定通知書には理由を付さなければなりません。
行政手続法では、申請者の権利を保護するために、審査基準の設定・公開義務(第5条)、標準処理期間の設定・公開(第6条)、審査開始義務(第7条)、理由提示義務(第8条)、情報提供義務(第9条)などが定められています。これらの規定は、生活保護申請においても当然に適用されます。
5.1 申請から決定までの法定期間
生活保護法第24条第5項では、申請から決定通知までの期間について明確な規定が設けられています。
- 原則14日以内: 保護の実施機関は、申請があった日から14日以内に保護の要否等を決定し、申請者に対して書面で通知しなければなりません4。
- 最長30日まで延長可能: 扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に時間を要する等の特別な理由がある場合は、申請から30日以内まで延長することができます4。
- 延長理由の明示: 処理期間を延長する場合は、決定通知書に処理が遅延した理由を明示することが求められています4。
行政手続法の観点からは、標準処理期間に関する規定もあります。行政機関は申請がその事務所に到達した時点で遅滞なく審査を開始する義務があり、恣意的な申請の放置や行政指導中であることを理由とする審査の放置などは許されません7。
標準処理期間を超過する場合の正当な理由としては、以下のようなものが考えられます。
- 不適法な申請の補正に要した期間
- 申請後に申請者が申請内容の変更を申し出たためその処理に要した期間
- 審査の必要のため申請者に資料の提出等を求めた場合、その提出等に要した期間7
しかし、これらの理由がある場合でも、生活保護法で定められた最長30日という期限を超えることはできません。
適法な申請手続きにおいては、申請者の権利を保障するために、法定期間内での処理が強く求められています。行政機関は、申請を受けた後、迅速かつ適正に審査を行い、法定期間内に決定を通知する義務があります。
6章 申請権が侵害された場合の法的対応
6.1 不作為の違法確認訴訟
申請権が侵害された場合、行政事件訴訟法に基づく「不作為の違法確認訴訟」を提起することができます。これは、行政庁が申請に対して相当の期間内に何らかの処分をすべきであるにもかかわらず、これをしない場合に、その不作為が違法であることの確認を求める訴訟です。
生活保護の申請が窓口で受理されなかった場合や、申請後に何の決定もないまま放置されている場合には、この不作為の違法確認訴訟が有効な手段となります。行政事件訴訟法第3条第5項では、「不作為の違法確認の訴え」を「行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟」と定義しています。
さいたま地方裁判所は2013年2月20日、埼玉県三郷市の福祉事務所が生活保護の申請を妨げ、申請があったにもかかわらず申請として扱わなかった事案について、申請権を侵害した違法行為であるとして損害賠償請求を認容する判決を下しました。日本弁護士連合会はこの判決を「生活困窮状態にある人を生活保護制度から不当に排除している生活保護行政の在り方に警鐘を鳴らすもの」として積極的に評価しています。
また、申請権侵害に対しては国家賠償請求訴訟を提起することも可能です。東京弁護士会の人権侵害救済申立事件に関する勧告書では、「相談者から生活保護の申請の意思があることを知り、若しくは、具体的に推知し得たのに申請の意思を確認せず、又は、扶養義務者ないし親族から扶養・援助を受けるよう求めなければ申請を受け付けない、あるいは、生活保護を受けることができない等の誤解を与える発言をした結果、申請することができなかったときなど、故意又は過失による申請権を侵害する行為をした場合には、職務上の義務違反が認められる」と指摘されています。
6.2 行政不服審査法に基づく不服申立て
行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政処分に不服がある場合の簡易迅速な救済手段として重要です。生活保護に関する不服申立ては、以下のような場合に可能です:
- 保護の申請が認められなかった(却下)場合: 審査請求が可能です。
- 保護の申請をしたが、何の決定もないまま放置されている場合: 不作為についての審査請求ができます。
行政不服審査法第2条では「行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができる」と規定されています。審査請求は、処分をした行政庁に上級行政庁(生活保護の処分の場合は都道府県知事など)がある場合はその上級行政庁、上級行政庁がない場合はその処分をした処分庁に対して行います。
審査請求の判断(裁決)についてさらに不服がある場合には、生活保護法第66条に基づき「再審査請求」を行うことも可能です。
なお、2016年4月に施行された改正行政不服審査法により、特定行政書士も一定の不服申立ての代理人となることができるようになりました。特定行政書士とは、行政書士法第1条の3第1項第2号に規定する研修を修了し、その旨の登録を受けた行政書士のことで、行政書士法第1条の3第2項に基づき、行政不服審査法に基づく不服申立ての手続きについて代理することができます。
ただし、特定行政書士が代理できるのは、行政不服審査法に基づく不服申立てのうち、処分についての審査請求、再調査の請求及び異議申立てに限られており、処分以外の事項についての不服申立ては代理できません。
生活保護の申請権侵害に対する法的対応としては、まず行政不服審査法に基づく審査請求を行い、それでも解決しない場合には行政事件訴訟法に基づく訴訟を提起するという段階的なアプローチが一般的です。ただし、審査請求前置主義が適用されない場合もあるため、状況に応じた適切な法的対応を選択することが重要です。
7章 行政機関の適切な対応のあり方
7.1 法律に基づく窓口対応の基準
行政機関、特に生活保護申請の窓口においては、申請権を保障するための適切な対応が求められます。行政手続法及び生活保護法に基づく窓口対応の基準として、以下の点が重要です。
- 申請意思の尊重: 相談者が申請の意思を示した場合は、必ず申請を受け付けなければなりません。申請をためらっている方に対しても、申請を促すなど相談者の申請権を尊重する必要があります。
- 適切な情報提供: 行政手続法第9条第2項に基づき、申請に必要な情報を提供する義務があります。生活保護制度の内容、申請方法、必要書類などについて正確な情報を提供しなければなりません。
- 対応時間の適切な設定: 長時間の対応は職員の判断力低下を招く恐れがあるため、一回の対応は概ね1時間程度を限度とすることが望ましいとされています13。ただし、これを理由に申請を妨げることは許されません。
- 複数職員による対応: 窓口対応は必ず2名以上で行うことが推奨されています1。これは、対応内容の正確な記録や、職員の安全確保のためです。
- 記録の作成: 対応内容は詳細に記録化することが重要です1。これは後の検証や、申請者の権利保護のために必要な措置です。
- 不当要求への対応: 暴力や脅迫を伴う要求に対しては、職員の安全を確保した上で、警察への通報など適切な対応をとることが必要です13。ただし、単なる申請行為を「不当要求」と誤認してはなりません。
自治体によっては、カスタマーハラスメント対策マニュアルを整備し、統一的な基準で窓口対応を行っている例もあります5。しかし、こうしたマニュアルが申請権侵害の口実として使われることがないよう注意が必要です。
7.2 申請と審査の法的分離の必要性
生活保護の申請と審査は法的に明確に分離されるべきであり、この分離は以下の理由から重要です。
- 申請権の保障: 行政手続法第7条は「申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない」と規定しています。これは申請と審査が別個の手続きであることを前提としています。申請の受付段階で実質的な審査を行い、申請を拒否することは法律違反です。
- 審査基準の明確化と公開: 行政手続法第5条は審査基準の設定と公開を義務付けています。申請と審査を分離することで、透明性のある審査が可能となります。
- 標準処理期間の遵守: 生活保護法第24条第5項は申請から決定までの期間を原則14日以内(最長30日)と定めています。申請と審査を明確に分離することで、この法定期間の遵守が確保されます。
- 適正手続の保障: 申請と審査を分離することで、申請者の手続的権利が保障されます。審査の過程で申請者に資料の追加提出を求めたり、意見を述べる機会を与えたりすることができます。
- 不服申立ての実効性確保: 行政不服審査法に基づく不服申立ての前提として、申請と審査の分離は不可欠です。申請が受理されなければ、不服申立ての対象となる「処分」が存在しないことになり、救済手段が制限されてしまいます。
生活保護の申請窓口では、「水際作戦」と呼ばれる申請抑制行為が問題となっています。これは申請と審査の法的分離が実務上無視され、申請前の相談段階で実質的な審査が行われている状態です。このような運用は行政手続法及び生活保護法の趣旨に反するものであり、改善が求められます。
行政機関は、申請権の保障と適正な審査の両立を図るため、申請と審査の法的分離を徹底し、法律に基づく適切な窓口対応を行う必要があります。
8章 まとめ:法に基づく申請権保障の重要性
生活保護の申請権は、憲法第25条に基づく生存権を具体化した重要な権利です。行政手続法と生活保護法は、この申請権を法的に保障する枠組みを提供しています。
行政手続法第7条は「申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない」と規定し、「受理」という概念を排除することで申請権の形骸化を防止しています3。この規定により、申請書が行政機関に物理的に到達した時点で審査義務が発生するという「到達主義」が確立されました。
生活保護法においても、第7条で申請保護の原則が明確に規定されており、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始する」とされています4。さらに、申請の方法についても、口頭による申請が認められるなど、申請者の負担を軽減する配慮がなされています46。
しかし現実には、いわゆる「水際作戦」と呼ばれる申請抑制行為が全国各地で報告されており、申請権が侵害されている実態があります。日本弁護士連合会は「申請権侵害を根絶するための書式・手順の改善」の必要性を指摘しています5。
申請権保障の重要性は以下の点にあります:
- 生存権の実質的保障: 申請権は憲法上の生存権を具体化するものであり、その侵害は基本的人権の侵害につながります。
- 法的安定性の確保: 法律に基づく適正な手続きを保障することで、行政の恣意的な判断を防止し、法的安定性を確保します。
- 社会的セーフティネットの機能強化: 申請権が適切に保障されることで、真に支援を必要とする人々に生活保護制度が行き届き、社会的セーフティネットとしての機能が強化されます。
- 行政の透明性と信頼性の向上: 申請権を尊重し、法律に基づく適切な対応を行うことで、行政の透明性と信頼性が向上します。
行政書士として、申請権保障の重要性を認識し、適切な法的助言を提供することは、法律専門家としての重要な役割です。生活保護の申請者が適切に権利を行使できるよう支援し、違法な申請拒否に対しては法的観点から問題点を指摘することが求められています。
最後に、申請権保障は単なる手続き上の問題ではなく、すべての人の尊厳ある生存を実現するための基盤であることを強調しておきたいと思います7。申請権が侵害されるような窓口の運用は直ちに是正されなければならず、法律に基づく適正な申請手続きの確立が急務です。
(終わり)