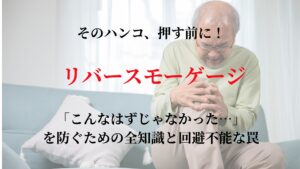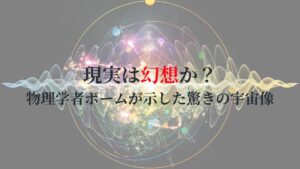建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。しかし「どんな工事でも許可が必要なのか」「許可を取らないとどうなるのか」など、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。本記事では建設業法第3条が定める許可制度の意義と概要について、実務経験豊富な行政書士が具体例を交えて解説します。建設業許可の必要性から申請先の判断方法まで、わかりやすく説明していきます。
建設業許可とは何か?〜第3条の許可制度の意義と概要〜
1章 建設業許可制度の意義と目的
1.1 建設業法が許可制度を設けた背景
建設業法第1条(目的)では、法律の目的について次のように規定しています。
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
この条文が示す通り、建設業法は単なる業界規制ではなく、「建設工事の適正な施工の確保」と「発注者保護」という二つの大きな社会的使命を持っています。
建設業許可制度が設けられた背景には、戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、建設需要の急増に伴い、技術力や資力に乏しい不良・不適格業者が乱立し、粗悪な工事や契約不履行などの問題が多発したという歴史があります。1949年(昭和24年)に制定された当初の建設業法では任意の登録制度でしたが、1971年(昭和46年)の大改正により現在の許可制度へと強化されました。
この許可制度により、一定の資質(技術力・経営力)を持たない者が建設業を営むことを禁止し、建設工事の品質確保と発注者保護を図るという基本的な枠組みが確立されたのです。
1.2 建設業許可が果たす社会的役割
建設業許可制度は、以下のような社会的役割を果たしています。
- 最低限の資質保証:許可基準(第7条・第15条)を満たした事業者のみが建設業を営めるようにすることで、技術力や経営力の最低水準を確保しています。
- 情報の非対称性の解消:一般の発注者は建設業者の技術力や経営状態を判断することが困難です。許可制度は、その判断材料を提供する役割を果たしています。
- 建設市場の健全化:不良・不適格業者を市場から排除し、健全な競争環境を整備することで、建設業全体の健全な発展を促進しています。
- 公共工事の品質確保:公共工事の入札参加資格として建設業許可が前提となっており、社会インフラの品質確保に貢献しています。
建設業は国民の生命・財産に直結する住宅やインフラを構築する重要な産業です。そのため、単なる営業の自由に委ねるのではなく、許可制度を通じて一定の規制を行うことが社会的に必要とされているのです。
1.3 許可制度による発注者保護の仕組み
建設業法第3条第1項では、建設業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと規定しています。
「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章の定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」
この許可制度は、以下のような仕組みで発注者保護を実現しています。
- 事前審査による品質保証:許可申請時に経営業務管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎など、一定の要件を審査します。これにより、工事を適正に遂行できる能力を持つ業者であることを行政が確認します。
- 情報開示による透明性確保:建設業許可情報は公開され、誰でも閲覧できます。発注者は業者選定の際にこれらの情報を参考にすることができます。
- 行政監督による継続的な質の担保:許可後も法令遵守状況を監視し、違反があれば監督処分(営業停止等)を行うことで、継続的な適正営業を促します。
- 許可表示義務による明示:建設業者は許可番号等を営業所や工事現場、契約書類等に表示する義務があり、発注者は許可業者であることを容易に確認できます。
このように、建設業許可制度は単なる参入規制ではなく、発注者が安心して建設工事を依頼できる環境を整備するための重要な社会的インフラとしての役割を果たしているのです。
建設業許可は「営業の自由」に一定の制限を加えるものですが、それは発注者保護と建設工事の品質確保という公共の利益のために必要な規制であり、建設業法の根幹を成す制度となっています。
2章 建設業法第3条の条文解説
2.1 第3条第1項:許可の原則
建設業法第3条第1項は、建設業許可制度の基本原則を定めた条文です。正確な条文は以下の通りです。
「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章の定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」
この条文の要点は以下の3つです。
- 建設業を営むには許可が必要:建設業を営むためには、原則として行政庁の許可を受ける必要があります。
- 許可行政庁の区分:許可を与える行政庁は、営業所の所在地によって決まります。
- 複数の都道府県に営業所がある場合:国土交通大臣許可
- 一つの都道府県内にのみ営業所がある場合:都道府県知事許可
- 営業所単位の許可:許可は会社全体ではなく、営業所ごとに必要です。ここでいう「営業所」とは、本店、支店その他の政令で定める場所をいいます。
この原則により、建設工事を請け負う事業者は、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、必ず許可を取得しなければなりません。無許可で建設業を営むと、建設業法第52条により「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という罰則が科される可能性があります。
2.2 第3条第1項但書:軽微な建設工事の例外
第3条第1項には但書があり、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。
「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」
この「軽微な建設工事」は、建設業法施行令第1条の2で次のように定義されています。
- 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
これを表にまとめると以下のようになります。
| 工事の種類 | 請負代金の基準 | 面積等の基準 |
|---|---|---|
| 一般の建設工事 | 500万円未満 | なし |
| 建築一式工事 | 1,500万円未満 | なし |
| 木造住宅の建築一式工事 | 金額基準なし | 延べ面積150平方メートル未満 |
ここで重要なのは、「軽微な工事」の判断は1件ごとに行われるという点です。例えば、同じ発注者から複数の小規模工事を受注した場合でも、契約がそれぞれ別であれば、各工事が軽微な工事に該当するかどうかを個別に判断します。
ただし、意図的に契約を分割して許可逃れをするような行為は、脱法行為として認められません。実質的に一体の工事と見なされる場合は、合算して判断されることがあります。
2.3 第3条第2項:29業種の区分
建設業法第3条第2項では、建設業の許可は29の業種ごとに与えられると規定しています。
「前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。」
建設業許可は「業種別許可制」を採用しており、営もうとする建設業の種類ごとに許可を受ける必要があります。例えば、土木工事と電気工事の両方を行いたい場合は、「土木工事業」と「電気工事業」の2業種の許可を取得する必要があります。
建設業法別表第一に定められた29業種は、大きく「一式工事」と「専門工事」に分類されます。
(1) 一式工事(2業種)
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
一式工事については、建設業法第2条第1項第1号および第2号で次のように定義されています。
第2条第1項第1号 「土木一式工事」とは、土木工作物を建設する工事(第三号に掲げるものを除く。)であつて、その工事を施工するために締結される請負契約において、土木工作物を建設する工事(第三号に掲げるものを除く。)以外の建設工事(第三号に掲げるものを除く。)を含むものをいう。
第2条第1項第2号 「建築一式工事」とは、建築物を建設する工事(第三号に掲げるものを除く。)であつて、その工事を施工するために締結される請負契約において、建築物を建設する工事(第三号に掲げるものを除く。)以外の建設工事(第三号に掲げるものを除く。)を含むものをいう。
つまり、一式工事とは、主たる工事(土木工作物または建築物の建設)に付帯する各種専門工事を含めて一括して請け負う工事を指します。
(2) 専門工事27業種のグループ分け
以下に主な専門工事業種を表にまとめます。
| 工事分野 | 業種 |
|---|---|
| 構造関連工事 | 大工工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 解体工事業 |
| 外装・仕上工事 | 左官工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 建具工事業 |
| 設備工事 | 電気工事業 管工事業 機械器具設置工事業 電気通信工事業 消防施設工事業 熱絶縁工事業 |
| 土木関連工事 | 舗装工事業 しゅんせつ工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 さく井工事業 造園工事業 |
各業種の許可を取得するためには、その業種に対応する専任技術者を営業所ごとに配置する必要があります。専任技術者には、それぞれの業種に対応した資格や実務経験が求められます。
このように、建設業法第3条は、建設業許可制度の基本的な枠組みを定めており、
①許可の原則
②軽微な工事の例外
③業種別許可制
という3つの重要な柱で構成されています。建設業を営む際には、自社の事業内容に照らして、どの業種の許可が必要か、また許可そのものが必要かどうかを正確に判断することが重要です。
3章 許可が必要となる「500万円以上の工事」とは
建設業法では、請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合に許可が必要となります。しかし、この「500万円」という金額の算定方法については、実務上様々な疑問が生じることがあります。ここでは、500万円の算定方法と具体的な事例を解説します。
3.1 500万円の算定方法
請負代金の額は、消費税を含む税込金額で判断します。また、注意すべき点として以下のようなケースがあります。
- 材料費込みの金額で判断:材料費と工事費を分けて契約している場合でも、合算した金額で判断します。
- 追加工事も含む:当初契約は500万円未満でも、追加工事により合計額が500万円以上になった場合は許可が必要です。
- 値引きがある場合:値引き後の最終的な請負金額で判断します。
- 下請工事の場合:元請との契約金額で判断します。元請が1,000万円の工事を受注し、そのうち600万円の部分を下請に出す場合、元請も下請も許可が必要です。
具体例
例1:材料支給の場合
A社が施工のみを400万円で請け負い、材料費200万円分は発注者が直接支払う場合
→ 実質的な工事価値は600万円ですが、A社の請負金額は400万円なので許可不要です。ただし、実質的に一体の取引と見なされる場合は許可が必要になることがあります。
例2:追加工事が発生した場合
当初450万円で契約したが、工事途中で60万円の追加工事が発生した場合
→ 合計510万円となるため、許可が必要です。この場合、追加工事の契約前に許可を取得する必要があります。
3.3 複数の工事を合算するケース
同一の発注者から複数の工事を請け負う場合、それぞれが別個の工事として契約されていれば、原則として個別に金額を判断します。しかし、以下のような場合は合算して判断することがあります。
- 一体性のある工事の分割契約:実質的に一体の工事を意図的に分割して契約している場合
- 短期間に連続して行われる同種の工事:同一現場で短期間に連続して行われる同種の工事
- 建設業許可逃れが目的と判断される場合:許可逃れを目的として意図的に契約を分割していると判断される場合
具体例
例3:同一敷地内の複数工事
同じマンションの1階店舗部分の内装工事(300万円)と2階住居部分の内装工事(400万円)を別々に契約した場合
→ 工事の性質、契約時期、施工時期が近接していれば、合算して700万円と判断され、許可が必要となる可能性があります。
例4:時期をずらした工事
4月に事務所の1階部分のリフォーム(400万円)を行い、半年後の10月に2階部分のリフォーム(350万円)を行った場合
→ 時期が離れており、それぞれが独立した工事と認められれば、個別に判断され、いずれも許可不要となる可能性が高いです。
3.4 【事例】境界線上の金額の判断例
実務では、500万円前後の工事について判断に迷うケースが多くあります。以下に、実際によくある境界線上のケースを紹介します。
事例1:追加工事による境界超え
ケース:
Aさんは自宅のリフォーム工事をB建設に480万円で依頼しました。工事開始後、Aさんの希望で浴室の仕様変更が追加され、追加工事費30万円が発生しました。
判断:
当初は500万円未満でしたが、追加工事により総額510万円となったため、B建設は建設業許可が必要です。追加工事の契約前に許可を取得するか、追加工事を別の許可業者に依頼する必要があります。
事例2:値引きによる境界調整
ケース:
C社は事務所の改装工事をD建設に見積もり依頼しました。見積金額は520万円でしたが、C社の予算の都合でD建設は20万円値引きし、最終的な契約金額は500万円ちょうどになりました。
判断:
最終的な契約金額が500万円ちょうどの場合、「500万円未満」の要件を満たさないため、建設業許可が必要となります。500万円以上の工事を請け負う場合は、たとえ500万円ちょうどであっても許可が必要です。
事例3:材料費分離による調整
ケース:
E社はオフィスの内装工事をF工務店に依頼しました。工事費は450万円、材料費は150万円で、材料はE社が直接購入することにしました。
判断:
F工務店の請負金額は工事費の450万円のみなので、許可は不要です。ただし、実質的にF工務店が材料の手配も行い、E社に材料費を別途請求するような形式的な分離契約の場合、脱法行為とみなされ、合算して判断される可能性があります。
事例4:複数現場の工事
ケース:
G不動産会社は、所有する3つのアパート(A棟、B棟、C棟)の外壁塗装工事をH塗装に依頼しました。それぞれの工事金額はA棟200万円、B棟180万円、C棟170万円で、同時期に工事を行う契約を結びました。
判断:
3つの建物は別々の現場ですが、同一発注者からの同種工事を同時期に請け負っており、合計550万円となります。このような場合、実質的に一体の工事と判断され、許可が必要となる可能性が高いです。
このように、「500万円以上の工事」の判断は単純な契約金額だけでなく、工事の実態や契約の経緯なども考慮して総合的に判断されます。境界線上の金額の工事を請け負う場合は、安全側に立って許可を取得しておくことをお勧めします。また、意図的な契約分割などによる許可逃れは脱法行為とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
4. 「軽微な工事」の範囲と判断基準
建設業法第3条第1項ただし書では、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」については、建設業許可が不要とされています。この「軽微な建設工事」の範囲を正確に理解することは、許可の要否を判断する上で非常に重要です。
4.1 500万円未満の工事の扱い
建設業法施行令第1条の2第1項では、軽微な建設工事について次のように定義しています。
「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円未満の建設工事(建築一式工事にあつては、工事一件の請負代金の額が千五百万円未満の建設工事又は延べ面積が百五十平方メートル未満の木造住宅工事)とする。」
この規定から、一般的な建設工事については、工事1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な工事」として許可不要となります。ここでいう「請負代金」には消費税が含まれます。
4.2 軽微な工事の具体例
例1:店舗内装リフォーム工事(480万円)
飲食店の内装全面リフォーム工事を480万円(税込)で請け負う場合、500万円未満なので許可不要です。
例2:事務所の電気設備工事(450万円)
事務所ビルの電気設備更新工事を450万円で請け負う場合も許可不要です。
注意点
- 一時的・臨時的な工事でも対象:たとえ一度きりの工事であっても、500万円以上であれば許可が必要です。
- 下請工事も同様:元請、下請を問わず、請負金額が500万円以上であれば許可が必要です。
- 工事途中での金額変更:当初は500万円未満でも、追加工事などにより500万円以上になった場合は、その時点で許可が必要となります。
- 複数の小規模工事:個々の工事が500万円未満でも、実質的に一体の工事と判断される場合は合算されます。
4.3 建築一式工事の特例(1,500万円未満)
建築一式工事については、他の工事種類よりも基準額が高く設定されています。具体的には以下の2つの基準のいずれかに該当すれば「軽微な工事」となります。
- 請負金額が1,500万円未満の建築一式工事
- 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(金額にかかわらず)
建築一式工事の特例の具体例
例3:小規模店舗の新築工事(1,400万円)
小規模な店舗の新築工事を建築一式で1,400万円で請け負う場合、1,500万円未満なので許可不要です。
例4:木造住宅の新築工事(1,600万円、床面積120平方メートル)
木造住宅の新築工事で、請負金額は1,600万円ですが、延べ床面積が120平方メートルの場合、150平方メートル未満の木造住宅工事に該当するため許可不要です。
注意点
- 「建築一式工事」の定義:建築一式工事とは、主体となる建築工事に加え、それに付帯する電気、給排水、空調などの設備工事も含めて一括して請け負う工事を指します。
- 専門工事との区別:内装工事のみ、電気工事のみなど、特定の専門工事のみを請け負う場合は、建築一式工事ではなく、それぞれの専門工事として500万円基準が適用されます。
- 木造住宅の範囲:木造住宅とは、主要構造部が木造の住宅を指し、店舗併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上を占めるものをいいます。
4.4 【チェックリスト】軽微な工事かどうかの判断ポイント
以下のチェックリストを使用して、自社が請け負おうとしている工事が「軽微な工事」に該当するかどうかを判断することができます。
(1) 基本的な判断ポイント
□ 工事種類の確認
- □ 建築一式工事か?
- □ その他の専門工事か?
□ 請負金額の確認
- □ 専門工事の場合:500万円未満か?
- □ 建築一式工事の場合:1,500万円未満か?
□ 木造住宅の場合
- □ 延べ面積が150平方メートル未満か?
- □ 主要構造部が木造か?
- □ 住宅用途が主か?
(2) 詳細な判断ポイント
□ 契約内容の確認
- □ 消費税を含めた総額で判断しているか?
- □ 材料費と工事費を合算しているか?
- □ 値引きがある場合、値引き後の金額で判断しているか?
□ 工事の一体性の確認
- □ 同一発注者からの複数工事を請け負う場合、実質的に一体の工事ではないか?
- □ 工事を意図的に分割していないか?
- □ 同一現場での連続した工事ではないか?
□ 追加工事の可能性
- □ 今後、追加工事が発生する可能性はないか?
- □ 追加工事を含めると500万円(建築一式は1,500万円)以上になる可能性はないか?
□ 契約形態の確認
- □ 元請工事か下請工事か?
- □ 下請工事の場合、自社の請負金額で判断しているか?
(3) 実務上の注意点
□ 境界線上の金額の場合
- □ 請負金額が基準額に近い場合、安全側に立って許可を取得することを検討しているか?
□ 営業としての継続性
- □ 「軽微な工事のみ」を請け負うことを継続的な営業としているか?
- □ 将来的に基準額以上の工事を請け負う可能性はないか?
□ 実態の確認
- □ 契約書の金額と実際の工事内容に乖離はないか?
- □ 脱法行為と見なされるような契約形態になっていないか?
このチェックリストを活用することで、建設業許可の要否を適切に判断することができます。ただし、境界線上のケースや判断に迷う場合は、所管の行政庁に相談するか、建設業法に詳しい専門家(行政書士など)に相談することをお勧めします。
「軽微な工事」の判断は、単に金額だけでなく、工事の実態や契約の経緯なども考慮して総合的に行われます。許可逃れと見なされるような行為は避け、適正な事業運営を心がけましょう。
5章 国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い
建設業許可には、国土交通大臣が行う「大臣許可」と都道府県知事が行う「知事許可」の2種類があります。どちらの許可を取得すべきかは、営業所の所在地によって決まります。この章では、両者の違いと判断基準について解説します。
5.1 二以上の都道府県にわたる営業所の場合
建設業法第3条第1項では、許可行政庁について次のように規定しています。
「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章の定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」
この条文から、許可行政庁の区分は以下のように整理できます。
- 国土交通大臣許可:二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
- 都道府県知事許可:一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業する場合
ここでいう「営業所」とは、建設業法第3条第1項の規定により、本店、支店その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。単なる工事現場の事務所や、契約締結権限のない連絡所などは「営業所」には該当しません。
具体例で考える
例1:東京に本店、大阪に支店がある建設会社
→ 2つの都道府県にまたがって営業所があるため、国土交通大臣許可が必要です。
例2:埼玉に本店、同じ埼玉県内に支店がある建設会社
→ 営業所がすべて埼玉県内にあるため、埼玉県知事許可が必要です。
例3:愛知に本店、三重に現場事務所がある建設会社(現場事務所では契約締結を行わない)
→ 三重の現場事務所は「営業所」に該当しないため、愛知県内にのみ営業所があるとみなされ、愛知県知事許可が必要です。
5.2 大臣許可と知事許可の実務上の違い
大臣許可と知事許可は、許可の効力や建設工事を請け負う権利に本質的な違いはありません。どちらの許可を持っていても、全国どこでも建設工事を請け負うことができます。しかし、実務上はいくつかの違いがあります。
1. 申請窓口と審査機関
大臣許可:
- 申請窓口:本店所在地を管轄する地方整備局等
- 審査機関:国土交通省(地方整備局等を通じて)
知事許可:
- 申請窓口:都道府県の建設業許可担当課
- 審査機関:都道府県
2. 審査基準と運用
基本的な許可基準は同じですが、運用面で若干の違いがあることがあります。例えば、専任技術者の実務経験の証明方法や、財産的基礎の審査における提出書類の詳細などに、地域による差異が生じることがあります。
3. 営業所の追加・廃止時の手続き
大臣許可:
- 新たな都道府県に営業所を設ける場合:変更届のみ
- 営業所を廃止して一つの都道府県内のみになった場合:知事許可への切り替えが必要
知事許可:
- 他の都道府県に新たに営業所を設ける場合:大臣許可への切り替えが必要
- 同一都道府県内で営業所を追加・廃止する場合:変更届のみ
4. 許可の更新時期
許可の有効期間は5年間で、大臣許可と知事許可で違いはありません。ただし、知事許可から大臣許可(またはその逆)に切り替えた場合、新たな許可の有効期間は切り替えた日から5年間となります。
5. 公共工事の入札参加資格
一部の公共工事の入札では、大臣許可と知事許可で評価が異なる場合があります。特に全国規模の大型工事では、大臣許可を持つ業者が有利になることもあります。ただし、これは許可自体の効力の違いではなく、発注者側の評価基準によるものです。
ここで重要なのは「営業所」の定義です。以下のチェックポイントで、各事務所が「営業所」に該当するかを判断しましょう。
5.3 営業所の判断チェックポイント
□ 契約締結権限
- □ その事務所で建設工事の請負契約を締結する権限があるか?
- □ 見積書や契約書にその事務所の所在地が記載されるか?
□ 常設性
- □ 一時的な現場事務所ではなく、恒常的に設置された事務所か?
- □ 事務所としての実体(看板、事務机、従業員等)があるか?
□ 独立性
- □ 単なる連絡所ではなく、ある程度独立した業務を行っているか?
- □ その事務所の代表者に一定の決裁権限が与えられているか?
□ 公的な登記・届出
- □ 法人登記上の本店または支店として登記されているか?
- □ 税務署等に事業所として届出されているか?
これらの要素を総合的に判断して、「営業所」に該当するかどうかを決定します。
5.4 許可申請の実務上のポイント
- 将来の事業展開を考慮する:
近い将来、他県に営業所を設ける計画がある場合は、最初から大臣許可を取得することも検討しましょう。 - 営業所の実態を確認する:
名目上の営業所でも、実態が伴わない場合は「営業所」と認められないことがあります。逆に、名目上は「連絡所」でも、実態として契約締結を行っている場合は「営業所」とみなされることがあります。 - 許可切り替えのタイミング:
知事許可から大臣許可(またはその逆)への切り替えは、新規許可申請と同様の手続きが必要です。更新時期に合わせて切り替えることで、手続きの効率化を図ることができます。
大臣許可と知事許可は、どちらが「上位」というわけではなく、営業所の所在地という客観的な基準によって区分されています。自社の営業所の状況を正確に把握し、適切な許可を取得することが重要です。
6. 許可を受けずに建設業を営むリスク
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うことは、建設業法違反となり、様々なリスクを伴います。この章では、無許可営業のリスクと実際に問題となったケースについて解説します。
6.1 建設業法違反の罰則(第47条)
建設業法第47条第1号では、無許可営業に対する罰則を次のように規定しています。
「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。」
つまり、許可を受けずに500万円以上の工事を請け負った場合、最大で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。これは法人だけでなく、その代表者や責任者個人も処罰の対象となる可能性があります。
また、建設業法第8条第8号では、建設業法違反により罰金刑に処せられた場合の欠格要件について規定しています。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この規定により、無許可営業で罰金刑に処せられた場合、その執行を終えてから5年間は建設業許可を取得できないことになります。また、懲役刑に処せられた場合は、同条第7号の「禁錮以上の刑に処せられ」た者として、同様に5年間は許可を受けられません。
6.2 罰則適用の実態
実際には、単純な無許可営業だけで即座に刑事罰が適用されるケースは多くありませんが、以下のような場合には積極的に摘発される傾向があります。
- 悪質な違反:意図的・継続的に無許可営業を行っている場合
- 他の違反との重複:無許可営業に加えて、不適切施工や詐欺的行為がある場合
- 事故や重大なトラブル:無許可工事で事故や重大な品質問題が発生した場合
- 通報や告発:競合他社や発注者からの通報・告発があった場合
6.3 無許可営業の実務上のデメリット
刑事罰のリスク以外にも、無許可営業には多くの実務上のデメリットがあります。
1. 公共工事の受注機会の喪失
公共工事の入札参加資格には建設業許可が必須条件となっています。無許可では公共工事を受注することができず、ビジネスチャンスが大幅に制限されます。
2. 民間工事での信用問題
多くの大手ゼネコンや不動産デベロッパーは、下請業者に建設業許可を求めます。無許可業者は、こうした優良な元請からの仕事を受注できない可能性が高くなります。
3. 建設業退職金共済制度の利用制限
建設業退職金共済制度(建退共)は、建設業許可業者を対象としており、無許可業者は加入できません。これにより、優秀な人材確保が困難になる可能性があります。
4. 融資や保証の制限
金融機関や保証会社は、建設業許可の有無を融資や保証の判断材料にすることがあります。無許可業者は資金調達が困難になる可能性があります。
5. 損害賠償請求のリスク
無許可営業が発覚した場合、発注者から契約の取消しや損害賠償を請求されるリスクがあります。特に工事途中で発覚した場合、代替業者への切り替えコストなども請求される可能性があります。
6. 行政処分による事業継続の困難
無許可営業が発覚した場合、行政指導を受け、是正を求められます。悪質な場合は営業停止命令等の行政処分を受ける可能性もあります。
6.4【事例】無許可営業で問題となったケース
実際に無許可営業が問題となった事例を紹介します。
事例1:公共工事入札時の発覚
ケース:
A建設は、県の発注する道路補修工事(1,200万円)の入札に参加しようとしました。しかし、入札参加資格審査の過程で、A建設が建設業許可を持っていないことが発覚しました。
結果:
A建設は入札参加資格を得られず、入札に参加できませんでした。また、県の建設業担当部署から行政指導を受け、今後の公共工事参加のためには速やかに許可を取得するよう勧告されました。
事例2:工事トラブルをきっかけに発覚
ケース:
B工務店は、マンションの大規模修繕工事(2,500万円)を無許可で請け負いました。工事中に施工不良が発生し、マンション管理組合との間でトラブルになりました。管理組合が調査を進める中で、B工務店が無許可であることが判明しました。
結果:
管理組合はB工務店との契約を解除し、既払金の返還と追加で発生した修復費用の損害賠償を請求しました。また、所管の行政庁に通報があり、B工務店は行政指導を受けるとともに、今後の許可申請に影響する可能性が生じました。
事例3:下請業者の無許可営業
ケース:
大手ゼネコンC社は、ショッピングモール建設工事の一部を下請業者D社(建設業許可あり)に発注しました。D社はさらに電気設備工事(800万円)を無許可業者E社に下請発注しました。工事完了後の施工体制台帳の確認過程で、E社が無許可であることが発覚しました。
結果:
発注者からC社に対して施工体制に関する改善要求があり、C社はD社に対して下請業者の選定基準の厳格化を求めました。E社は今後C社関連の工事を受注できなくなり、D社との取引も制限されることになりました。また、所管行政庁からE社に対して許可取得の指導がありました。
事例4:意図的な契約分割による許可逃れ
ケース:
F社は、オフィスビルの改装工事(総額1,200万円)を無許可業者G社に依頼しました。G社は許可逃れのため、工事を「内装工事480万円」と「電気設備工事480万円」の2つの契約に分割して請け負いました。しかし、実態は一体の工事であり、G社の元従業員からの通報で、この事実が所管行政庁に知られることになりました。
結果:
G社は建設業法違反として行政指導を受け、是正勧告を受けました。また、今後の許可申請において、過去の無許可営業の事実が審査に影響する可能性が生じました。F社も発注者としての責任を問われ、今後の公共工事発注において、コンプライアンス体制の見直しを求められました。
これらの事例からわかるように、無許可営業は発覚するリスクが常にあり、発覚した場合には事業継続に大きな影響を与える可能性があります。建設業を営む上では、適切に許可を取得し、法令を遵守することが長期的な事業成功の基盤となります。
500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、事前に建設業許可を取得することを強くお勧めします。許可取得には一定の要件と手続きが必要ですが、専門家(行政書士等)のサポートを受けることで、円滑に進めることができます。
7章 まとめ:建設業許可の重要性
これまで建設業法第3条に基づく許可制度について詳しく解説してきました。最後に、建設業許可の重要性と許可取得のメリット、そして許可申請の基本的な流れについてまとめます。
7.1 許可取得のメリット
建設業許可を取得することには、法令遵守という側面だけでなく、事業者にとって多くのメリットがあります。
1. 受注機会の拡大
- 公共工事への参入:国や地方公共団体が発注する公共工事の入札参加資格の前提条件となります。
- 大手企業からの受注:多くの大手企業や不動産デベロッパーは、下請業者に建設業許可を求めています。許可を持つことで取引先の幅が広がります。
- 大型工事の受注:500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を合法的に請け負うことができます。
2. 信用力・ブランド力の向上
- 対外的な信用:建設業許可は、一定の技術力・経営力を持つ事業者であることの証明になります。
- 顧客からの信頼:「国や都道府県から認められた事業者」という安心感を顧客に与えることができます。
- 広告効果:会社案内やホームページ、名刺などに許可番号を記載することで、信頼性をアピールできます。
3. 資金調達の円滑化
- 融資の優遇:金融機関は建設業許可を持つ事業者に対して、融資の審査を有利に進める傾向があります。
- 公共工事前払金保証制度:公共工事の前払金を受け取るための保証制度を利用できます。
- 建設業専門の融資制度:建設業許可業者向けの各種融資制度を活用できます。
4. 人材確保・育成の優位性
- 建設業退職金共済制度(建退共):建設業許可業者は建退共に加入でき、従業員の福利厚生を充実させることができます。
- 技術者の確保:専任技術者の配置が必要となるため、技術力の向上につながります。
- 人材の定着:許可業者としての安定した経営基盤は、従業員の定着率向上にも寄与します。
5. 法的リスクの回避
- 罰則の回避:無許可営業による罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を回避できます。
- 契約トラブルの防止:適法な状態で営業することで、契約の有効性に関するトラブルを防止できます。
- 行政処分リスクの回避:無許可営業による行政処分を受けるリスクを回避できます。
7.2 許可申請の基本的な流れ
建設業許可の申請手続きは、以下のような流れで進みます。
1. 許可要件の確認と準備
- 許可要件の確認:経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎などの要件を満たしているか確認します。
- 必要書類の準備:登記簿謄本、決算書、納税証明書、経営業務管理責任者・専任技術者の証明書類など、多数の書類が必要です。
- 営業所の確保:本店や支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を確保します。
2. 申請書類の作成
- 許可申請書:所定の様式に基づき、会社情報、役員情報、営業所情報、申請業種などを記入します。
- 添付書類の作成:経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書、財務諸表、工事経歴書など、多数の添付書類を作成します。
- 誓約書等の作成:欠格要件に該当しないことの誓約書など、各種誓約書を作成します。
3. 申請と審査
- 申請先の確認:営業所の所在地に応じて、国土交通大臣または都道府県知事に申請します。
- 申請手数料の納付:申請時に所定の手数料を納付します(新規申請の場合、通常9万円程度)。
- 書類審査:提出書類に基づき、許可要件を満たしているかどうかの審査が行われます。
- 実地調査:必要に応じて、営業所の実態調査が行われることがあります。
4. 許可の取得と許可後の対応
- 許可通知:審査に通過すると、許可通知書が交付されます(申請から通常1〜2ヶ月程度)。
- 標識の掲示:営業所と建設工事現場ごとに、建設業の許可票を掲示する必要があります。
- 帳簿の備付け:建設工事ごとに所定の事項を記載した帳簿を作成・保存する必要があります。
- 各種変更手続き:商号、代表者、営業所所在地などに変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
- 5年ごとの更新:許可の有効期間は5年間であり、継続して営業する場合は更新手続きが必要です。
7.3 次回予告:許可の区分(一般と特定)について
本記事では、建設業許可制度の基本的な仕組みと第3条の解説を中心に行いました。次回は、建設業許可の区分である「一般建設業」と「特定建設業」の違いについて詳しく解説します。
一般建設業と特定建設業では、必要な資格要件や請け負える工事の範囲、下請契約の制限などが異なります。どちらの許可を取得すべきか、自社の事業内容に合わせた選択方法についても解説しますので、ぜひご覧ください。
建設業許可は、単なる法的義務ではなく、事業拡大と安定経営のための重要なステップです。許可取得には一定の要件と手続きが必要ですが、その効果は長期的な事業発展に大きく寄与します。許可申請に不安がある場合は、建設業許可申請を専門とする行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、建設業許可の新規申請から更新、変更手続きまで、豊富な実績と専門知識を活かしてサポートしております。お気軽にご相談ください。
(シリーズ2へ続く)