日本全国で増加の一途をたどる空き家問題。2018年の総務省の調査では全国の空き家率は13.6%に達し、約849万戸もの住宅が空き家となっています。
しかし、この社会問題は見方を変えれば大きなビジネスチャンスでもあります。地域によって異なる空き家の実態と需要を正確に把握し、適切な活用戦略を立てることで、社会課題の解決と収益確保の両立が可能です。
本記事では、都市部・地方・観光地など地域特性に応じた空き家の賃貸活用方法と、成功への具体的なアプローチを解説します。空き家所有者や不動産投資を検討している方必見の内容です。
地域別空き家活用ガイド:賃貸需要を見極め成功に導く実践戦略
1章 はじめに:空き家活用の現状と可能性
日本の空き家問題は年々深刻化しており、2023年の総務省の調査によれば、全国の空き家数は900万戸を突破し、総住宅数の13.8%を占めるに至りました12。これは約7軒に1軒が空き家という計算になります。さらに株式会社野村総合研究所の予測では、2033年までに空き家率は30.4%に上昇し、約3軒に1軒が空き家になると見込まれています7。
この急増する空き家の背景には、高齢化の進行や相続問題があります。国土交通省の空き家所有者実態調査によれば、空き家の取得理由で最も多いのは「相続」で、全体の54.6%を占めています9。特に団塊世代が後期高齢者となる2025年以降は、相続の件数がさらに増加し、それに伴い空き家も増えると予想されています。
しかし、この社会問題は見方を変えれば大きなビジネスチャンスでもあります。2023年12月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、空き家の活用拡大を図る「空家等活用促進区域」の創設や、市区町村が空家の活用や管理に取り組む団体を「空家等管理活用支援法人」に指定できる制度が開始されました410。
また、全国各地の自治体では空き家対策として様々な支援制度を設けています。東京都内だけでも、空き家相談窓口の設置、専門家派遣制度、空き家バンク、リノベーション補助金、除却費用の助成など多様な支援が行われています6。
空き家を放置することのリスクも高まっています。適切に管理されていない空き家は「特定空家」や「管理不全空家」に指定される可能性があり、その場合「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることもあります9。
このような状況の中、空き家の賃貸活用は所有者にとって有効な選択肢の一つとなっています。地域の特性を理解し、適切な活用戦略を立てることで、社会課題の解決と収益確保の両立が可能です。
本稿では、都市部・地方・観光地など地域特性に応じた空き家の賃貸活用方法と、成功への具体的なアプローチを解説します。空き家所有者や不動産投資を検討している方に、地域ごとの需要の見極め方や活用のポイントを提供し、空き家問題の解決と資産活用の両立を目指します。
空き家に関するご相談、管理等のご依頼は、行政書士 小川洋史事務所、小川不動産株式会社まで
2章 地域別の空き家率と市場動向
都市部vs地方:空き家率の格差とその背景
日本全国の空き家率は2023年時点で13.8%に達し、約900万戸が空き家となっています3。しかし、この数値は地域によって大きく異なります。
都市部と地方の間には明確な空き家率の格差が存在します。一般的に地方部では空き家率が高く、都市部では相対的に低い傾向にあります。この格差が生じる主な背景として、都市部への人口集中が挙げられます。若年層を中心に就職や進学を機に都市へ移動し、地方の実家や祖父母の家が空き家になるケースが多く見られます1。
また、地方では産業の衰退により働く場が少なく、若者が戻ってくる機会が減少していることも要因となっています1。さらに、都市部では住宅需要が比較的強いため、空き家が発生しても再利用される可能性が高い一方、地方では需要の低さから空き家が放置されやすい状況があります。
ただし、都市部でも空き家問題は無縁ではありません。東京都の空き家率は2018年の10.6%から2023年には11.0%へと0.4%上昇しています3。これは世帯数の増加率(+3.8%)が総住宅数の増加率(+4.2%)を下回っていることが原因と考えられます10。特に賃貸用の空き家増加が主因となっており、投資目的の供給が実需を上回っている状況が見られます。
空き家率ワーストランキングから見る地域特性
空き家率の高い地域には特徴的なパターンが見られます。2023年の調査によると、空き家率が高い都道府県は山口県(19.4%)、大分県(19.1%)、徳島県(21.2%)、愛媛県(19.8%)など、主に西日本の地方が上位を占めています3。
特に注目すべきは、2018年から2023年にかけて空き家率が増加した都道府県のランキングです。トップ10には大分県(+2.3%)、秋田県(+2.1%)、北海道(+2.1%)、長崎県(+1.9%)、山口県(+1.8%)などが含まれており、四国・九州などの西日本と東北地方が多く挙がっています3。
また、空き家の種類にも地域特性が表れています。山梨県や長野県のように別荘地を多く抱える地域では「二次的住宅」としての空き家が多く、長野県軽井沢町では二次的住宅空き家率が63%と突出しています8。一方、過疎化が進む地域では「その他の住宅」(賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家)の割合が高い傾向にあります。
これらの地域特性を理解することは、空き家活用戦略を立てる上で重要な視点となります。観光資源のある地域では宿泊施設への転換、過疎地域では地域コミュニティの拠点としての活用など、地域の特性に合わせた対策が求められています。
人口動態と空き家増加の相関関係
空き家増加と人口動態には強い相関関係があります。統計分析によれば、高齢化率と空き家率、高齢単身世帯率と空き家率、死亡率と空き家率の間には正の相関関係が確認されています5。つまり、高齢者の割合が高い地域ほど空き家率も高くなる傾向があるのです。
少子高齢化の進行は空き家問題の主要因となっています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本の総人口は2053年には1億人を下回り、2065年には9,000万人を割り込むと予測されています9。この人口減少は特に地方部で顕著であり、住宅の空き家化を加速させています。
また、都市部への人口集中も空き家問題を悪化させる要因です。地方から若者が都市部に移り住むことで地方の空き家が増え、さらに都市部でも仕事や学校の関係で住居を転々とする人が多く、空き家が発生しやすくなっています2。
空き家の発生原因を見ると、相続による取得が大半を占めています6。高齢者が亡くなると、家を相続する人がいない、または相続したとしても住む予定がないため、家が放置されるケースが多くなっています1。特に所有者が遠方に住んでいる場合、定期的な管理が難しくなり、空き家が放置される傾向があります2。
このように、空き家問題は人口減少、高齢化、都市部への人口集中など、複合的な人口動態の変化によって引き起こされています。今後も日本の人口構造の変化に伴い、空き家問題はさらに深刻化する可能性が高いと言えるでしょう。
3章 地域特性に応じた空き家の賃貸活用戦略
都市部の空き家活用:コンパクト物件と利便性の価値
都市部の空き家活用においては、限られたスペースを最大限に活かすコンパクト設計と立地の利便性が重要な価値となります。都市部では単身世帯や少人数世帯の需要が高く、これらのターゲット層に向けた戦略的なリノベーションが効果的です。
国土交通省の住宅市場動向調査によれば、都市部における賃貸住宅の選択理由として「通勤・通学の利便性」が最も高く、次いで「最寄り駅までの距離」「日常の買い物の利便性」が上位を占めています。このことから、駅や商業施設へのアクセスの良さを前面に出した物件訴求が有効といえるでしょう。
また、都市部では若年層を中心に「シェアハウス」の需要も高まっています。一般社団法人日本シェアハウス協会の調査では、首都圏のシェアハウス市場は2015年から2020年にかけて約1.5倍に拡大しており、特に20代〜30代の単身者からの支持を集めています。古い戸建て住宅をシェアハウスにリノベーションすることで、一人当たりの家賃収入を最大化できる可能性があります。
さらに、テレワークの普及により「ワークスペース付き住宅」の需要も高まっています。リクルート住まいカンパニーの調査では、コロナ禍以降、在宅勤務に適した住環境を求める転居ニーズが20%以上増加しています。空き家をリノベーションする際に、快適なワークスペースを確保することで、差別化を図ることができるでしょう。
都市部の空き家活用では、建物の老朽化対策も重要です。耐震補強や断熱性能の向上など、安全性と快適性を高めるリノベーションが必須となります。東京都などでは耐震改修工事に対する補助金制度も充実しており、これらを活用することでコスト削減も可能です。
地方の空き家活用:ニッチ需要の発掘と差別化
地方の空き家活用では、大都市にはない地域の魅力を活かしたニッチ需要の発掘と、他物件との明確な差別化が成功の鍵となります。
近年注目されているのが「二地域居住」や「地方移住」を検討する層向けの活用です。内閣府の調査によれば、東京圏在住者の約50%が地方移住に関心を持っており、特にコロナ禍以降、その割合は増加傾向にあります。こうした潜在的移住者向けに「お試し居住」用の物件として空き家を活用する取り組みが各地で始まっています。
また、地方特有の自然環境や文化を活かした特色ある賃貸住宅への転換も効果的です。例えば、古民家の風情を残しながら現代的な設備を導入する「古民家再生」は、都会では味わえない暮らしを求める層に人気があります。島根県雲南市の「NIPPONIA 雲南 吉田」では、空き家となった古民家を宿泊施設やカフェに改修し、年間約1万人の観光客を集める成功事例となっています。
さらに、地方では高齢者向けの住まいとしての活用も有効です。厚生労働省の推計によれば、2025年には75歳以上の高齢者が全人口の18%を超える見込みであり、バリアフリー設計の賃貸住宅への需要は今後も増加すると予想されます。空き家をバリアフリーリノベーションし、高齢者向け住宅として提供することで、安定した需要を確保できる可能性があります。
地方の空き家活用では、自治体の支援制度を活用することも重要です。多くの自治体では空き家バンク制度や改修費用の補助金制度を設けており、例えば長野県飯田市では最大100万円の改修費補助を行っています。こうした制度を上手く活用することで、初期投資の負担を軽減できます。
観光地近接エリアの空き家:宿泊施設への転換
観光地やその近接エリアにある空き家は、宿泊施設への転換が有効な活用策となります。特に近年は「一棟貸し」や「体験型宿泊施設」など、従来のホテルや旅館とは異なる宿泊形態への需要が高まっています。
観光庁の宿泊旅行統計調査によれば、2019年の日本国内の延べ宿泊者数は約5億9,600万人泊に達し、コロナ禍による一時的な落ち込みはあったものの、2023年には回復基調に転じています。特に訪日外国人観光客は2023年に約2,500万人を記録し、今後も増加が見込まれています。
空き家を民泊施設として活用する場合、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく届出が必要です。この法律では年間提供日数の上限を180日と定めていますが、自治体によっては条例でさらに制限を設けている場合もあります。一方、旅館業法に基づく「簡易宿所」として登録すれば、営業日数の制限なく運営することが可能です。
特に注目すべきは「一棟貸し」形式の宿泊施設です。観光地での一棟貸しの平均稼働率は50〜60%程度で、一泊あたりの単価も通常の宿泊施設より高く設定できる傾向があります。例えば、京都市内の古民家を改修した一棟貸し施設では、一泊3〜5万円の料金設定でも高い稼働率を維持している事例があります。
また、地域の文化や伝統を体験できる「体験型宿泊施設」への転換も効果的です。農業体験や伝統工芸体験など、その地域ならではの体験プログラムを提供することで、宿泊だけでなく体験料も含めた収益が見込めます。長野県飯山市の「なじょもん」では、古民家を改修した宿泊施設で地元の食材を使った料理体験を提供し、高い評価を得ています。
宿泊施設への転換を検討する際は、周辺の観光資源や交通アクセスの充実度を十分に調査することが重要です。また、季節変動の大きい観光地では、オフシーズンの対策も考慮する必要があります。地域イベントの開催や長期滞在者向けのプランなど、年間を通じた安定した集客戦略が求められます。
空き家を宿泊施設に転換する際には、消防法や建築基準法などの法的要件を満たす必要があり、改修費用が高額になる場合もあります。しかし、観光庁や自治体による宿泊施設改修の補助金制度も充実しており、例えば「観光産業等生産性向上資金」などを活用することで、初期投資の負担を軽減できる可能性があります。
空き家に関するご相談、管理等のご依頼は、行政書士 小川洋史事務所、小川不動産株式会社まで
4章 需要を見極めるための地域分析手法
空き家の賃貸活用において成功を収めるためには、その地域の特性や将来性を正確に把握することが不可欠です。本章では、地域分析の三つの重要な視点から、空き家活用の需要を見極めるための具体的な手法を解説します。
地域の人口動態と将来予測
地域の人口動態は空き家の需要を左右する最も基本的な指標です。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」によれば、令和2(2020)年から令和7(2025)年にかけて東京都を除く46道府県で総人口が減少し、令和22(2040)年から令和27(2045)年以降は東京都を含むすべての都道府県で総人口が減少すると予測されています1。
特に人口減少が著しい地域として、秋田県では令和32(2050)年の総人口が令和2(2020)年と比べて4割以上少なくなると予測されています。同様に、青森県(61.0)、岩手県(64.7)、高知県(65.2)、長崎県(66.2)など11県では3割以上の人口減少が見込まれています1。
一方で、全国の総人口に占める割合は、東京都や神奈川県では今後徐々に上昇し、令和32(2050)年には東京都(13.8%)、神奈川県(8.1%)となる見通しです1。また、埼玉県や千葉県、愛知県といった大都市圏に含まれる県と、滋賀県、福岡県、沖縄県でも全国の総人口に占める割合がやや上昇すると予測されています1。
人口動態を分析する際には、以下の点に注目することが重要です:
- 年齢別人口構成:若年層が多い地域か高齢者が多い地域かによって、需要のある住宅タイプが異なります。
- 世帯構成の変化:単身世帯の増加や核家族化の進行状況を把握することで、適切な間取りや設備の方向性が見えてきます。
- 社会増減:転入超過か転出超過かを分析し、人口移動の傾向を把握します。特に15~20年の産業の雇用吸収力を従業地就業者数増減率からみると、千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・奈良県・福岡県・沖縄県では、産業構造要因と地域特殊要因の両方が人口増加に寄与しています13。
将来人口の予測には「コーホート要因法」が最も信頼できる方法として評価されており、国などが行う将来人口推計の標準的な方法となっています3。この方法を活用して、対象地域の5年後、10年後、20年後の人口予測を行うことで、投資の長期的な見通しを立てることができます。
交通アクセスと生活インフラの充実度
交通アクセスの良さは、住宅需要を大きく左右する要素です。国土交通省の資料によれば、都市間移動の速達性を表す都市間連絡速度を見ると、幹線道路ネットワークが未整備の地域では遅い傾向にあり、諸外国と比較すると、日本の都市間の速達性は低い水準にあります4。
一方で、日本の交通インフラ建設市場は、2023年の1,105億米ドルから2032年には1,743億米ドルへと、年平均成長率5.20%で成長すると予測されています6。第2次交通政策基本計画(~2025年度)や第5次社会資本整備重点計画(~2025年度)に基づき、高規格幹線道路等の未整備区間の整備が推進され、都市間移動の速達性が高まることが期待されています4。
交通アクセスと生活インフラを評価する際のポイントは以下の通りです:
- 公共交通機関へのアクセス:最寄り駅やバス停までの距離、運行頻度、主要都市部へのアクセス時間を調査します。国土交通省の住宅市場動向調査によれば、都市部における賃貸住宅の選択理由として「通勤・通学の利便性」が最も高く、次いで「最寄り駅までの距離」が重視されています。
- 道路網の整備状況:高速道路のインターチェンジや主要幹線道路へのアクセスの良さを確認します。
- 生活利便施設の充実度:商業施設、医療機関、教育施設、公共施設などの生活インフラの充実度を評価します。「日常の買い物の利便性」も賃貸住宅選択の重要な要素となっています。
- 今後の開発計画:自治体の都市計画や交通網の整備計画を調査し、将来的な利便性の向上可能性を見極めます。
交通インフラの相対規模(対県内総生産比、就業者一人当たり)は地方圏の方が大きい傾向にありますが、これは「均衡ある国土の発展」や「多極分散型国土の形成」といったビジョン・計画の下で、公共投資による地域開発、地域間経済格差の是正が図られたためです5。
地域の産業構造と雇用状況
地域の産業構造と雇用状況は、住宅需要の質と量を決定づける重要な要素です。地域によって産業構造は大きく異なり、それに伴い就業構造にも特徴が現れます。
産業別の就業者数の変化を見ると、製造業は2015年の936万人から2025年には798万人に減少する一方、サービス業は2020年の2938万人をピークに、2025年には減少に転じ2908万人になると予測されています7。特に宿泊業・飲食サービス業は2020年をピークに減少に転じ、医療・福祉の就業者数も2020年を境に増加幅が縮小すると見込まれています7。
地域の産業構造と雇用状況を分析する際のポイントは以下の通りです:
- 主要産業の把握:地域の基幹産業や成長産業を特定し、その安定性や将来性を評価します。都市部では、南関東地域は管理・事務職、専門的・技術的職業の従事者の割合が高く、近畿地域では販売職やサービス職従事者が多い一方、東海地域では生産工程・労務、輸送・通信従事者の割合が多くなっています8。
- 雇用の安定性:主要企業の経営状況や雇用の安定性を調査します。2010年代の日本の経済成長は、情報・通信業ではなく、製造業等がけん引していた点も考慮する必要があります12。
- 賃金水準:地域の平均賃金や産業別の賃金水準を把握し、賃料設定の参考にします。地域の産業は大別すると「グローバル・域外開拓型」と「ローカル・域内循環型」に分けられ、特にローカル・域内循環型のサービス産業は地域の雇用の大宗を担うものの、現状では賃金・生産性ともに低水準にとどまっている傾向があります10。
- 新規産業の誘致状況:自治体の産業振興策や企業誘致の状況を調査し、将来的な雇用創出の可能性を見極めます。
地域別の就業者増減率を産業別に分解して寄与度をみると、90年代を通じてサービス業の寄与度が大きく、96年以降は、サービス業の寄与が特に大きくなっています11。また、2000年代において都道府県の人口分布に最も影響を及ぼしているのは、製造業の雇用環境を巡る地域間格差であることが分析結果から明らかになっています9。
これらの地域分析手法を総合的に活用することで、空き家活用の需要を正確に見極め、効果的な投資戦略を立てることができます。特に重要なのは、単一の指標だけでなく、人口動態、交通アクセス、産業構造の三つの視点から総合的に分析することです。そうすることで、表面的な数値だけでは見えてこない地域の真の潜在力や課題を把握することができるでしょう。
5章 賃貸需要が見込める空き家のタイプと条件
空き家を賃貸物件として活用する際には、現代の住まいのニーズを的確に捉えることが重要です。本章では、特に需要が見込める空き家のタイプと条件について、単身者・高齢者向け需要、テレワーク対応物件、そしてリノベーションによる付加価値創出の観点から解説します。
単身者・高齢者向け需要の拡大
近年、単身世帯と高齢者世帯の増加に伴い、これらの層をターゲットにした賃貸住宅の需要が急速に拡大しています。総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、賃貸物件を利用する高齢単身世帯の割合は現在3割を超えており、今後もさらに伸びていくことが予想されています1。
単身者向け物件の特徴
単身者向け物件で重視すべき点は以下の通りです:
- コンパクトな間取り: 1R〜1LDKの効率的な空間設計
- 立地条件: 通勤・通学の利便性が高い場所
- セキュリティ: 特に女性単身者に配慮した防犯設備
- 共用スペース: シェアハウスなど、コミュニティを形成できる空間
特に都市部では、単身者向けのシェアハウス需要が高まっています。一般社団法人日本シェアハウス協会の調査によれば、首都圏のシェアハウス市場は2015年から2020年にかけて約1.5倍に拡大しており、特に20代〜30代の単身者からの支持を集めています。古い戸建て住宅をシェアハウスにリノベーションすることで、一人当たりの家賃収入を最大化できる可能性があります。
高齢者向け物件の特徴
高齢者向け賃貸住宅では、以下の要素が重要となります:
- バリアフリー設計: 手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材の使用3
- 医療・介護施設へのアクセス: 病院やデイサービスなどの近接性2
- コミュニティ形成: 孤独死防止のための見守りサービスや交流スペース
- 緊急時対応: 24時間対応の見守り・緊急コールシステムの導入3
高齢者向け住宅市場は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)だけでなく、一般賃貸住宅においても拡大しています。特に年金受給額が将来減少することが予想される中、リーズナブルな費用で入居できる一般賃貸物件が、高齢者の受け皿になることが期待されています2。
高齢者向け賃貸住宅の管理においては、入居者の状況変化に対応できる体制づくりが重要です。具体的には、緊急連絡先の確保、地域の医療機関との連携、見守りサービスの導入などが挙げられます2。
テレワーク時代の新たな住まい方に対応する物件
コロナ禍を経て、テレワークの普及により住まいに求められる機能が大きく変化しました。この変化を捉えた空き家活用が新たな需要を生み出しています。
テレワーク対応物件の特徴
テレワーク対応物件で重視される要素は以下の通りです:
- 専用ワークスペース: 書斎や在宅オフィススペースの確保6
- 通信環境: 高速インターネット回線の整備
- 遮音性: オンライン会議に対応できる防音設備
- 間取りの拡大: 1LDKから2LDK以上の間取りへのニーズ増加6
テレワークの普及により、都市部から郊外や地方への移住ニーズも高まっています。内閣府の調査によれば、東京圏在住者の約50%が地方移住に関心を持っており、特にコロナ禍以降、その割合は増加傾向にあります。
地方の空き家活用とテレワーク
地方の空き家をテレワーク拠点として活用する動きも活発化しています:
地方自治体の中には、空き家をテレワーク拠点として改修する場合に補助金を出すケースも見られます。例えば、石川県金沢市では「ようこそ金沢テレワーク空き家活用事業」、奈良県桜井市では「空き家利活用テレワーク施設等整備補助事業」など、最大1,000万円の補助が受けられる事業が展開されています5。
リノベーションによる付加価値創出
空き家の価値を最大化するためには、適切なリノベーションによる付加価値創出が不可欠です。単なる修繕ではなく、新たな価値を生み出すリノベーションが求められています。
リノベーションとリフォームの違い
リノベーションとリフォームは明確に異なります:
リノベーションを行うことで、家そのものの価値を高め、新たな活用方法を見出すことができます。
付加価値を生み出すリノベーションの例
効果的なリノベーションの例としては以下が挙げられます:
- 間取りの変更: 現代のライフスタイルに合わせた空間設計
- 設備の刷新: システムキッチン、ユニットバス、洋式トイレへの交換7
- 断熱性能の向上: 省エネ性能を高める改修
- デザイン性の向上: 内外装のデザイン性を高め、差別化を図る
特に注目すべきは、築40年の空き家をリノベーションした場合、物件価値が2倍以上に上昇したケースも報告されています9。
リノベーションの費用対効果
リノベーションの費用対効果を高めるポイントは以下の通りです:
- ターゲット設定: 入居者層(単身者、ファミリーなど)を明確にする9
- コスト効率: 高級すぎない、耐久性と機能性重視の設備を選ぶ9
- 省エネ対策: 断熱性能向上、省エネ設備導入で長期コストを削減する9
- 独自性: 周辺物件と差別化できる特徴を付加する9
例えば、500万円の空き家を購入し、300万円でリノベーションを行う場合、総投資額は800万円程度に抑えられます。これは、新築物件への投資と比較して、大幅にコストを抑えることができる点が魅力です9。
活用できる補助金制度
空き家のリノベーションには、様々な補助金制度を活用できます:
これらの補助金を上手く活用することで、リノベーションの初期投資の負担を軽減できます。
空き家の賃貸活用において成功するためには、現代のニーズを的確に捉え、適切なターゲット設定とリノベーションによる付加価値創出が不可欠です。単身者・高齢者向け需要の拡大、テレワーク時代の新たな住まい方への対応、そして効果的なリノベーションによる価値向上を意識した戦略的な取り組みが求められています。
空き家に関するご相談、管理等のご依頼は、行政書士 小川洋史事務所、小川不動産株式会社まで
6章 地域別成功事例から学ぶ空き家活用のポイント
空き家活用の成功事例は地域特性によって大きく異なります。都市部、地方、観光地それぞれの特徴を活かした事例から、効果的な活用方法とそのポイントを解説します。
6.1 都市部での再生事例
都市部の空き家活用では、限られた空間の有効利用と周辺環境との調和が重要です。
大阪市の古民家再生プロジェクト
大阪市では、明治から戦前にかけて建てられた古民家が立ち並ぶ住宅街を「空き家を住宅以外に用途変更する」ことで再生するプロジェクトが成功を収めています。古民家をイタリアンレストランに改装したことを皮切りに、30以上の空き家を欧米の街をイメージしたおしゃれな店舗に改装し、カフェ・居酒屋・美容室など多種多様な業態の店舗に再生しました2。
この事例の成功ポイントは、「空き家を賃貸住宅に改装したものの、入居者が退去して新たな空き家が生まれる」という連鎖を解消し、地域全体の活性化につなげた点にあります。
東京都練馬区のリノベーション賃貸
東京都練馬区では、古い一軒家を全面的にリノベーションし、現代的でおしゃれな住空間に変えることで、賃料を相場より高めに設定できた事例があります。自治体の補助金を活用してリノベーション費用を抑え、数ヶ月以内に新しい入居者が決まりました10。
都市部での空き家活用では、以下のポイントが重要です:
- 用途変更による差別化: 単なる住宅としてではなく、商業施設やシェアスペースなど新たな用途への転換
- デザイン性の重視: 現代的なニーズに合わせたデザイン性の高いリノベーション
- 周辺環境との調和: 地域の特性を活かしつつ、新たな価値を創出する工夫
6.2 地方での活性化事例
地方の空き家活用では、地域コミュニティとの連携や地域資源の活用が成功の鍵となります。
栃木県栃木市の空き家バンク活用
栃木県栃木市は、空き家バンク制度を活用して全国で最も多くの空き家の賃貸や売却の成約を果たした成功事例です。売主・買主双方のメリットを最大化するために、リフォーム費用の補助や税金の軽減措置などを用意し、高齢者や低所得者が活用しやすい環境を整えました4。
長野県下諏訪町の職人誘致プロジェクト
長野県下諏訪町の御田町商店街では、職人を地域に誘致し空き家を活用する取り組みが行われています。20年間の取り組みで30店舗以上が開業し、空き家をなくすことに成功しました411。
商店主やNPOが主体となり、「匠の町」として機械工房や衣類品など、ものづくり商店街として若者や創業を志す人々を誘致し、地域の活性化及び空き店舗ゼロを達成しています11。
徳島県神山町のサテライトオフィス誘致
徳島県神山町は、サテライトオフィス誘致の取り組みにより、空き家活用と移住促進を同時に進めています。サテライトオフィスが設置されることで、地域に新たな働き手が訪れ、空き家が改修されて住宅や事業所として利用されるようになっています4。
地方での空き家活用の成功ポイントは以下の通りです:
- 地域特性を活かした活用法: 地域の産業や文化に合わせた空き家の活用
- 自治体の支援制度の活用: 補助金や税制優遇などの支援制度を最大限に活用
- 移住・創業支援との連携: 空き家活用と移住促進や創業支援を組み合わせた総合的な取り組み
6.3 観光地での転用事例
観光地やその近接エリアでは、空き家を宿泊施設や体験施設として活用することで、観光資源としての価値を高めることができます。
兵庫県篠山市の分散型ホテル
「篠山城下町ホテルNIPPONIA(ニッポニア)」は、築100年以上の古民家を含む4棟を宿泊施設として活用し、城下町全体をひとつのホテルに見立てています。国家戦略特区として2015年から始まったホテル事業で、国内外の観光客に好評を博しています56。
このプロジェクトでは、古民家の趣を残しつつ、快適な宿泊環境を整える改修が行われました。特に地元の伝統工芸や素材を取り入れたインテリアが観光客に好評です6。
山梨県小菅村の分散型ホテル
人口700人の小さな山村である山梨県小菅村は、地域に分散した古民家を再生し、「NIPPONIA小管源流の村」として村全体がひとつのホテルのようになっています。2018年6月の改正旅館業法の施行後は、国家戦略特区でなくても地域に分散した施設をまとめて一つのホテルとして営業許可を得られるようになりました5。
長崎県小値賀島の古民家ステイ
長崎県小値賀島の「古民家ステイ」は、島内に点在する空き家を改修し、分散型ホテルとして運営しています。観光客が島全体を散策しながら、地域の自然や文化を体験できる仕組みを提供している点が特徴的です6。
観光地での空き家活用の成功ポイントは以下の通りです:
- 地域資源との連携: 地域の観光資源や文化資源と連携した活用
- 体験価値の提供: 単なる宿泊だけでなく、地域ならではの体験を提供
- 地域全体での取り組み: 点在する空き家を面として捉え、地域全体で取り組む姿勢
これらの成功事例から学べることは、空き家活用には地域の特性を理解し、その地域ならではの価値を創出することが重要だということです。都市部では利便性と差別化、地方ではコミュニティとの連携、観光地では体験価値の提供が、それぞれ成功の鍵となっています。
7章 空き家賃貸活用の法的・制度的サポート
空き家の賃貸活用を成功させるためには、様々な法的・制度的サポートを活用することが重要です。本章では、自治体の補助金・支援制度、空き家バンク制度、税制優遇措置について解説します。
7.1 自治体の補助金・支援制度
全国の自治体では、空き家の活用を促進するためのさまざまな補助金や支援制度を設けています。これらを活用することで、初期投資の負担を軽減し、より効果的な空き家活用が可能になります。
改修費用の補助
多くの自治体では、空き家の改修費用に対する補助金制度を設けています。例えば、大阪市では「空家利活用改修補助制度」を実施しており、空き家の利活用に向けたインスペクション(既存住宅状況調査)や、住宅の性能向上に資する改修、非営利団体等による地域まちづくりに資する用途への改修に対して補助を行っています1。この制度では、平成12年5月31日以前に建築された住宅で、3か月以上空き家であることなどが条件となっています。
また、テレワーク環境整備のための設備工事も補助対象となるケースが増えています。大阪市の制度では、性能向上に資する改修工事としてテレワーク環境のための設備工事も補助対象に含まれています1。
企業向け支援制度
企業が空き家を活用する場合の支援制度も充実しています。例えば、長野県木曽町では「企業版空き家活用補助金」を実施しており、保養目的やテレワークオフィス、サテライトオフィスとして活用するために空き家を取得した町内外の企業等に対し、取得費用及び改修費用の一部を補助しています2。補助率は1/2で、上限額は80万円となっています。
移住者向け支援制度
移住促進を目的とした空き家活用支援も各地で行われています。和歌山県有田市では、空き家・空き地バンクに登録された家の購入や改修、空き地へ新築する場合に費用の一部を補助しています3。また、沖縄県石垣市では、空き家バンクを利用して空き家を改修した場合、最大50万円の補助金が交付される制度があります3。
7.2 空き家バンク制度の活用法
空き家バンクは、空き家の所有者と利用希望者をマッチングするシステムで、多くの自治体で運営されています。この制度を効果的に活用することで、空き家の賃貸活用の可能性が広がります。
空き家バンクの仕組み
空き家バンクは、各自治体が地域内にある空き家の情報を集めて公開する仕組みです9。空き家所有者は「空き家バンク」へ物件を登録すると、物件情報を「買いたい・借りたい」と考えている空き家利用希望者へ広く情報を提供することができます4。
例えば、大仙市の空き家バンクでは、市内の空き家を「売りたい・貸したい」と考えている空き家所有者と「買いたい・借りたい」と考えている空き家利用希望者を結び付けるサービスを提供しています4。
登録の手続き
空き家バンクに物件を登録する際の手続きは自治体によって異なりますが、一般的には以下のような流れになります:
- 宅地建物取引業者との媒介契約(管理委託契約)を締結
- 空き家バンク登録申込書などの必要書類を自治体に提出
- 登録手続き完了後、自治体のホームページ等で空き家物件情報が公開される4
なお、空き家バンクのなかには、所有者が不動産業者などに一定額を払って登録物件の管理を委託する例もあります5。
全国版空き家バンクの活用
2017年秋からは、全国共通の空き家バンクのサイト運用が開始されています。民間不動産サービスのLIFULL(ライフル)とアットホームの2社へ運営を委託し、全国の空家情報を一つにまとめることで、地方ごとにばらばらであった表示形式、掲載項目などを統一し、使い勝手を向上させています5。
これにより、地方版空き家バンクの課題であった「紹介する物件数が少なく、対象地域も限られるため、利用率が低い」という問題が改善されています。
7.2 税制優遇措置の活用
空き家の賃貸活用においては、様々な税制優遇措置を活用することで、経済的なメリットを最大化することができます。
固定資産税の軽減措置
住宅用地には固定資産税の特例措置が設けられており、200平方メートル以下の小規模住宅用地については、固定資産税が1/6に軽減されます10。ただし、空き家が「特定空家」と認定されると、この優遇措置が解除され、固定資産税が最大6倍に増加する可能性があります10。
2025年4月に予定される建築基準法改正では、再建築不可物件の所有者にとって、固定資産税優遇措置が見直される可能性があります11。これまでは「建物が存在している限り」優遇措置を受けられる場合がありましたが、法改正により、建築基準法を満たさない物件が優遇対象外となる可能性が指摘されています。
空き家の改修・活用に関する税制優遇
空き家をリフォームして賃貸物件や事業用施設に転用する場合、一定の条件を満たせば所得税や法人税の減税を受けることができます。例えば、耐震改修を行った場合、工事費用の一部を所得税から控除できる制度があります6。
また、相続した空き家を売却する場合の特例措置もあります。相続または遺贈により取得した居住用家屋や敷地を一定の期間内に売却し、一定の要件に当てはまる場合には、譲渡所得の額から最大3,000万円まで控除することができます8。
地域特性に応じた税制優遇
地域によっては、独自の税制優遇措置を設けている場合もあります。例えば、神奈川県小田原市鴨宮では、空き家の固定資産税の負担を軽減するための制度が提供されています7。
空き家を賃貸物件として活用する場合、収入を得ながら税金の一部を相殺することが可能です。また、リノベーションを施すことで空き家の価値を高め、エコリフォームによる固定資産税の軽減措置を活用することで、長期的なコスト削減が可能となります7。
空き家の賃貸活用を成功させるためには、これらの法的・制度的サポートを最大限に活用することが重要です。自治体の補助金・支援制度、空き家バンク制度、税制優遇措置を組み合わせることで、初期投資の負担を軽減しながら、効果的な空き家活用を実現することができます。
空き家に関するご相談、管理等のご依頼は、行政書士 小川洋史事務所、小川不動産株式会社まで
8章 空き家投資のリスク管理と長期的視点
8.1 出口戦略の重要性
空き家を賃貸活用する際には、将来的な出口戦略を事前に検討しておくことが極めて重要です。出口戦略とは、投資物件を手放す際の計画であり、その有無によって最終的な利益が大きく変わってきます。
空き家投資において出口戦略が必要な理由は主に二つあります。
一つ目は、利益の望めない賃貸物件を所有し続ける意味がないためです。空き家は投資物件としての側面があるため、利益が出ない時点で手放す必要があります。出口戦略がないと負債を抱えてしまうリスクが高くなります1。
二つ目は、将来的に子供への相続で迷惑をかける可能性があるためです。
出口戦略として検討すべき主なパターンには以下のようなものがあります:
- 収益物件のまま売却する: 入居者がいる状態で売却し、引き渡しの直前まで家賃収入を得る方法です。高値で売却するためには入居率を上げることと高い家賃設定が重要になります6。
- 居住用物件として売却する: 賃借人が退去したタイミングで、自己居住用として買主に売却する方法です。特にファミリー向け物件は需要が高い傾向にあります6。一般的に居住用物件としての売却価格は、投資用物件としての売却価格よりも高くなります。
- 用途変更して売却する: 例えば、郊外の空き家を民泊施設に転換することで投資価値を高める方法があります。青梅市の事例では、売れなかった空き家を民泊化することで実質利回り11.8%の投資物件として価値を創出し、不動産投資家からの購入希望を集めることに成功しています2。
出口戦略を立てる際には、将来の人口動向や需要を予測することが欠かせません。購入物件のエリアは将来的に人口が増えるのか、需要が高まるのかを見極める必要があります6。特に2025年以降は空き家問題がさらに深刻化すると予測されており4、政府も空き家の有効活用や解体促進のための新たな制度を導入する予定です8。
また、地域特性に応じた出口戦略も重要です。「活用可能性の高い空き家」の比率が高く、一般世帯数の増加が見込まれる地域(栃木県、茨城県、大阪府、静岡県、群馬県、広島県など)では中古住宅としての活用ポテンシャルが高いため、中古住宅流通を見据えた戦略が有効です3。一方、「活用可能性の高い空き家」の比率が全国平均を上回るものの、一般世帯数の減少が見込まれる地域(高知県、鹿児島県、徳島県、和歌山県、愛媛県、長野県など)では、用途変更を促進する戦略が考えられます3。
9章 まとめ:地域特性を活かした空き家活用の未来展望
空き家問題は日本全国で深刻化しており、2023年時点で総住宅数の13.8%に相当する900万戸以上が空き家となっています4。しかし、この社会問題は見方を変えれば大きなビジネスチャンスでもあります。
地域特性を活かした空き家活用は、単なる問題解決にとどまらず、地域活性化や新たな価値創造につながる可能性を秘めています。栃木県栃木市のように空き家バンク制度を活用して全国で最も多くの空き家の賃貸や売却の成約を果たした事例や、長野県下諏訪町のように職人を地域に誘致して空き家を活用し、20年間の取り組みで30店舗以上が開業した事例など、各地で成功事例が生まれています5。
今後の空き家活用においては、以下の点が重要になるでしょう:
- 地域特性の正確な把握: 人口動態、交通アクセス、産業構造など多角的な視点から地域を分析し、その特性に合った活用方法を見出すこと。
- 多様なニーズへの対応: 単身者・高齢者向け需要、テレワーク対応、体験型宿泊施設など、変化する社会ニーズを捉えた活用方法を検討すること。
- 制度的サポートの活用: 自治体の補助金・支援制度、空き家バンク、税制優遇措置など、様々な制度的サポートを最大限に活用すること。
- 長期的視点と出口戦略: 初期投資から出口戦略まで、長期的な視点で空き家活用を計画すること。
- 持続可能性の追求: 一時的な活用にとどまらず、地域コミュニティの持続的発展につながる活用方法を模索すること。
2025年に向けて、政府は空き家の有効活用や解体促進のための新たな制度を導入する予定であり、これにより地域の活性化や住環境の改善が進むことが期待されています8。また、中古住宅市場は成長を続けており、政府も中古住宅流通を後押ししていることから、空き家活用ビジネスは大きな可能性を秘めています7。
空き家問題は日本社会の大きな課題ですが、地域特性を理解し、適切な活用戦略を立てることで、社会課題の解決と経済的価値の創出を両立させることが可能です。空き家を「問題」ではなく「資源」として捉え直し、地域の特性を活かした創造的な活用を進めることで、持続可能な地域社会の実現に貢献していくことが求められています。
(おわり)
空き家に関するご相談、管理等のご依頼は、行政書士 小川洋史事務所まで


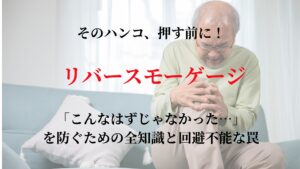
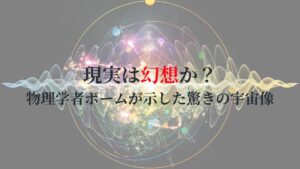






コメント